みなさんは「現在完了形」をどのように教わりましたか?
おそらく「have + 過去分詞」で覚えているかと思います。
そして日本の英語教育であれば「過去分詞」は次の2パターンで学習します。
- have + 過去分詞 ⇒ 完了形
- be + 過去分詞 ⇒ 受動態(受身)
どうやらこの2つはぜんぜん違う意味に見えます。
過去分詞の意味が「受動」と「完了」に変化する仕組みがよくわかりませんよね?
英語の現在完了はヘンテコ
そもそも have は「持つ」という意味の「動詞」だったはずです。
一体、have の「持つ」という意味はどこへ行ってしまったのでしょうか?
そしてさらにみなさんを混乱させる現在完了の英文が存在します。
I am become Death.
『我は死神となれり。』
実はこれは英語圏では比較的よく知られた「現在完了の文」なんです。
少し古風な文章であるのは事実ですが、ちゃんと英文法の基本は機能しています。
「ええ!? I am become ってどうやって現在完了になるの!?」
と思いませんか?思いますよね?
このような疑問はすべて正しい疑問です!
私は日本で英語を勉強していたころ、同じように思っていました。
英文法をシステム的に理解しようとするなら、こういう疑問があって当然です。
ところが実は、その疑問への答えはシンプルです。
なぜなら「have + 過去分詞」の用法は「例外」だからです。
そのため「基本ルール」として理解することは不可能です。
もちろん英語にはイディオム・語法に代表されるように「例外」がいくつかあります。
しかし「have + 過去分詞」は本来の文法から「ちょっと変化した例外」なんです。
つまり昔の用法ではちゃんと「基本ルール」で機能していたものなんです。
では「have + 過去分詞」のカラクリを理解するために、まずは「過去分詞」のおさらいをします。
過去分詞の意味と機能
最初に申し上げました通り「have + 過去分詞」は「例外ルール」として機能しています。
次のポイントが理解できているなら、そのまま進んでください。
- 過去分詞の名称の由来
- 動詞の過去形と同じ形だから過去分詞
- 過去時制とは全く関係ない!
- 分詞は動詞を形容詞に変えて使う品詞
- 現在分詞と過去分詞は形容詞!
- 動詞の過去形と同じ形だから過去分詞
- 過去分詞の機能
- 完了相(行動が実現済であることを示す)
- 受動態(目的語を主語に変える機能)
- 英文法用語の「相 aspect」
- 行動が「どの程度実現したか?」を意味する文法用語
- 過去分詞は「完了相 perfect aspect」を発動可能
- 現在分詞は「進行相」を発動
- 英文法用語の「態 voice」
- 英語の動詞の初期設定は「能動態」になる。
- 目的語を持つ動詞を「他動詞」とよぶ。
- 他動詞の過去分詞だけが「受動態 passive voice」を発動する。
これらは日本の英文法解説だと詳しくないことが多いです。
次のブログで「過去分詞の基本ルール」を解説しているので参照ください。
では基本から例外に変化していくプロセスをみていきましょう。
完了の have は「助ける動詞」
おそらく英文法書には「have + 過去分詞」の『have は助動詞』と載っています。
助動詞は英語で「auxiliary verb」といいます。
日本語では「助動詞」の解説はあまり詳しくないことが多いです。
ところが、この「助動詞 auxiliary verb」をさらに細かく分類した2種類の文法用語が存在します。
- 法助動詞: modal auxiliary verb
- will, shall, can, may, must
- would, should, could, might
- 第一助動詞: primary auxiliary verb
- be動詞
- have
これら2グループがまとめて「助動詞 auxiliary verb」と呼ばれています。
完了相をつくる have は「第一助動詞」というグループに入ります。
なぜなら「完了の have」は will や can とは別物なんです。
そして will や can などは「法助動詞」は、英語のご先祖様であるゲルマン語グループに由来する特別な助動詞です。
この理由は「法 mood」と呼ばれる「話し手の認識・判断」を表現する機能を持つからです。
あまりなじみがないかもしれませんが「仮定法 subjunctive mood」に使われている「法 mood」のことです。

そもそも文法用語の「助動詞」は「不定詞(動詞の原形)や分詞を助ける動詞」という意味です。
古い英語では will や can も「動詞の原形」を目的語にした動詞でした。
なぜなら古英語では「動詞の原形」は「動詞の名詞用法(~すること)」だったからです。
そのため今でもゲルマン語グループに入るドイツ語やオランダ語の「法助動詞」は完全な動詞としても使います。
現代英語の法助動詞だけが「動詞の機能」を失ってしまいました。
ここで現代英語の仕組みで2つをまとめてみます。
- 法助動詞:昔は動詞だったけど、今は「法 mood」の専門になりつつある
- 第一助動詞:分詞を助けるホンモノの動詞
というわけで be動詞と have ですが、こちらこそ正真正銘の「助動詞」です。
なぜなら「現在分詞と過去分詞を助ける動詞」だからです。
- I am doing it.(動詞+現在分詞)
- I have done it.(動詞+過去分詞)
この be 動詞や have を「助ける動詞」とするのはフランス語も同じです。
フランス語には英語の will や can のような法助動詞がなく、普通の動詞しかありません。
なぜならロマンス語グループのフランス語はゲルマン語の英語と大きく違う動詞のシステムを持つからです。
そのフランス語でも avoir(have)や être(be)を過去分詞とペアにすると「助動詞」と呼びます。
なぜなら avoir や être は「過去分詞を助ける完全なる動詞」だからです。
フランス語も英語も be動詞 や have こそ「助ける動詞」なんです。
正確な文法用語の定義に従えば「正統派の助動詞」と教わるべきものは be と have というわけです。
つまり「過去分詞とペアの have は 動詞」と知るだけで一気に理解が進みます。
英語の助動詞を詳しく知りたい方はこちらをどうぞ。
have + 過去分詞の成り立ち
では「have + 過去分詞」はどのように生まれたのでしょうか?
この話はすべて英語の Wikipedia に載っています。
ではちょっと長いですが、みていきましょう。(日本語は私が注釈しながら訳したものです)
The have-perfect developed from a construction where the verb meaning have denoted possession, and the past participle was an adjective modifying the object, as in I have the work done.
「have を使った完了表現は、所有を意味する動詞(have)と『 I have the work done.』のように目的語(the work)を修飾する形容詞である過去分詞(done)を組み合わせたものから発展したものです。」
https://en.wikipedia.org/wiki/Perfect_(grammar)
過去分詞は「動詞が変化した形容詞」です。
これは英文法では「超基本ルール」なので確認しておきます。
そして次のように続きます。
This came to be reanalyzed, with the object becoming the object of the main verb, and the participle becoming a dependent of the have verb, as in I have done the work.
「ここから文法理解が再分析され『I have done the work』のように目的語(have の目的語としての the work)が過去分詞(done)を動詞と解釈した場合の目的語(done の目的語としての the work)になり、そして過去分詞(done)は動詞である have に従属するものとなった。」
https://en.wikipedia.org/wiki/Perfect_(grammar)
そもそも「他動詞の過去分詞」には「受動態+完了相」の両方がデフォルトで発動します。
ですがその前に、ここで日本の英語解説でよくある困った話をおさえてきます。
なぜだかわかりませんが、過去分詞の機能が「完了」と「受身」のどちらかしか発動しないような解説が多くあります。
英語の仕組みでは「相」と「態」は同時に発動します。
それは現在分詞を見ればすぐにわかります。
- I am doing it.
- 私は ~である している それを
- ≒ 私はそれをしています。
現在分詞に「進行相(行動が実行中)」と「能動態(~する)」が同時に発動していますよね?
現在分詞にできることが過去分詞にできないわけはないんです。
ここで分詞の持つ「相 & 態」の仕組みをおさえておきます。
- 現在分詞
- 進行相
- 能動態(すべての動詞に発動)
- 過去分詞
- 完了相
- 受動態(他動詞だけに発動)
このように他動詞の過去分詞で「完了相」を意味したい場合には「受動態」も同時に発動してしまいます。
それゆえ have it done の構造がもともと採用されていました。
- I have done it.(今の現在完了)
- I have it done.(昔の現在完了)
つまりムリヤリ和訳すると「それが完了されたように持つ」という意味だったんです。
この昔の表現は英語の基本ルールに従っているものです。
さらにドイツ語ではこのように昔の英語と同じ仕組みで「現在完了」を作ります。
しかし「自動詞」の場合は話が違ってきます。
ポイントは「他動詞」でなければ「受動態」を発動できないことにあります。
The construction could then be generalized to be used also with intransitive verbs.
「次に、(本来なら be + 過去分詞 で完了を構成するはずの)自動詞でも使われるまでに(have + 過去分詞の)構文が一般化されたと思われる。」
https://en.wikipedia.org/wiki/Perfect_(grammar)
基本ルールであれば自動詞の過去分詞(形容詞)を繋げるのは have ではなく be動詞です。
例文をみていきましょう。
- He is gone.
- I am come.
こういった「be + 自動詞の過去分詞」はちょっと古い文章などではカンタンに見つかります。
自動詞の過去分詞はただの形容詞なので、そもそも他動詞の have は必要ないはずなんです。
なぜなら have を使うのは「目的語」を置く必要があったからです。
ところが現代英語では自動詞の過去分詞であってもムリヤリ「have + 過去分詞」の構造をつくります。
この自動詞でもムリヤリに「have+過去分詞」をつくる話が一番ややこしいです。
そこで自動詞はひとまず保留して have を使える「他動詞の過去分詞」から詳しく見ていきましょう。
have + 過去分詞の文法解説
まずここまでのポイントは have を「動詞」とするところからスタートしています。
さきほどお伝えしたように「助動詞」の定義は「分詞を助ける動詞」だからです。
過去分詞とは「完了相」と「受動態」の機能を持つ動詞の形容詞変化形です。
過去分詞の品詞は「形容詞」なので「補語 C」に入れることができます。
それゆえ元々は、動詞 have の第五文型(SVOC)の「補語 C」にハマるように使われていました。
- I have it done.
- 私は現在、それが完了した状態を持っています
- have ⇒ 現在時制の動詞
- done ⇒ 過去分詞(完了相と受動態)
・・・の2つのコンビネーションという理解になります。
実は古英語の時代は語順ルールが弱く、どちらでも機能することはできました。
ところが現代英語は語順ルールが厳しくなり「have + 過去分詞」を固定するようになりました。
このような経緯で「have + 過去分詞」で「完了状態を持つ」という意味の「動詞」として機能するようになります。
それではわかりやすく図解してみます。

注意ですが「have + 過去分詞」を1つの「動詞」とするのは例外用法です。
動詞 have だけでは「完了相」の意味を持つことはできません。
過去分詞だけなら「完了相」と「受動態」の形容詞になってしまいます。
それゆえ「have + 過去分詞」がセットになって初めて「完了の動詞」という理解が必要になります。
英語の場合は have + 過去分詞を分離して理解することはできなくなっています。
ところが、実はこれで話は終わりではありません。
この「have + 過去分詞」の昔の使い方にはある一つの条件がありました。
それは have の後に来る「O C の関係が受動でなければならない」ということです。
図解するとこうなります。

このことは言い換えれば、過去分詞が「受動態」を持たないとダメだということです。
受動態をつくるにはまず他動詞の目的語が必要です。
そして「目的語をとる機能」は他動詞だけが持ちます。
そのため「他動詞の過去分詞」でなければ「受動態」をつくれないんです。
ここで「能動態 ⇔ 受動態」の切り替えの仕組みを知りたい方はこちらをどうぞ。
つまり昔の用法では「補語 C」に入るのは「他動詞の過去分詞」に限定されていたんです。
- have 目的語 他動詞の過去分詞(〇)
- have 目的語 自動詞の過去分詞(✖)
では「受動態」をもつ他動詞の過去分詞だけが「完了相」をつくることができたのでしょうか?
そんなことはありません。
ちゃんと「自動詞」でも「完了相」を作ることができます。
では次に、自動詞の完了相を見ていきましょう。
be + 自動詞の過去分詞の成り立ち
ではまず「自動詞」の確認です。
まず動詞には五文型(SVOCの5パターン)があります。
その5種類の中で「目的語 O」をもたない動詞のことを自動詞と言います。
- 第1文型「SV」をとる動詞は「自動詞」
- 第2文型「SVC」をとる動詞は「不完全自動詞」
自動詞(SV と SVC パターンの動詞)には目的語がありません。
それゆえ自動詞の過去分詞には「受動態」が適応されないのです。
そうなると、自動詞の過去分詞には「完了相」のみ適応されます。
その結果、自動詞の過去分詞の場合は have を使うことはできなかったんです。
では自動詞で「完了を表現する」には、どうすればいいのでしょうか?
実はもうすでに中学1年でその答えを習っています。
中学でならう「現在進行形」とは「be動詞 + 現在分詞」のことです。
現在分詞は「進行相(行動がすすんでいる)」を意味する表現です。
自動詞の過去分詞には受動態の機能がありません。
だから have をつかいません。その代わり、ただの形容詞として扱います。
つまり自動詞の過去分詞も現在分詞と同じ扱いでOKです。
ということは・・・普通に be動詞と組み合わせればいいんです!
★現在分詞は「進行相」の意味を持つ形容詞です。
- He is walking.
- 彼は歩いている
- I am feeling sick.
- 私は気分が悪い
★過去分詞は「完了相」を意味を持つ形容詞です。
- He is risen.
- 彼は蘇った。
- I am become Death.
- 我は死神となれり。
いかがでしょう?
2つ目はブログの冒頭で紹介させていただいた文です。
一見「意味不明」にみえるのには理由があります。
これらの表現は古典から引用したものだからです。
- 聖書 the Bible
- バガバッド・ギータ the Bhagavad-Gita(古代インドの叙事詩)
この完了用法は古い形ですから、あえて例文を引用するとなると原典が古くなってしまうんです・・・悪しからず。
ちょっと現実離れした表現ではありますが、それはさておき文法構造を詳しく見ていきましょう。
He is not here for he is risen
“he is risen” は聖書にでてくる表現です。
2000年近くの歴史をもつ聖書には英訳だけでも様々なものがあり、現代の表現から、古めかしい英文まで様々なものがあります。
ここで紹介するのは New King James Version (NKJV) です。
では、実際に使われている英文を引用し、解説に移ります。
He is not here; for He is risen, as He said. Come, see the place where the Lord lay.
『もう(He = イエスは)ここにはおられない。かねて言いわれたとおりに、よみがえられたのである。さあ、イエス(the Lord)が納おさめられていた場所をごらんなさい。』
マタイの福音書28章6節(Matthew 28:6 NKJV)
rise は自動詞で「立ち上がる、上る」を意味します。
その活用形は rise – rose – risen となります。
イエス・キリストが死後、「もう復活した」ということを表現するため risen という完了相をもつ過去分詞が使われています。
それゆえ “He is risen.” で「彼(イエス・キリスト)が蘇った」いう意味になります。
ただ、あくまでもこれは古い表現になります。
より現代の用法に近い “has risen” も載っていますので、参考までに見ていきましょう。
“He is not here; he has risen, just as he said. Come and see the place where he lay.”
Matthew 28:6 (New International Version)
こちらは「has + 過去分詞」を使って現在完了の動詞として表現しています。
学校でもよくみる現代の表現ですので、おなじみかと思います。
be + 自動詞の過去分詞の文法解説
ではここから文法解説に進んでいきます。
現代英語で have を無理やり使うことになったので、文法解釈も変わります。

現代では「自動詞」であっても「have + 過去分詞」でまとめて「動詞」としての解釈になります。
これこそが日本で「受動態」と「現在完了」と別物と刷り込まれる過去分詞の本来の姿です。
そこから時代を経て be 動詞をむりやり have に置き換えたのが現代英語の「例外用法」です。
これによって「自動詞(受動態なし)」か「他動詞(受動態)」かの区別をせずに「完了の動詞」をつくれる便利な表現ができました。
では続けて SVC の過去分詞をみていきましょう。
I am become Death, the destoryer of the worlds.
I am become Death, the destroyer of the worlds.
『我は死神なり、世界の破壊者なり(私は死神、世界の破壊者となった)』
the Bhagavad Gita
これは古代インドの叙事詩である the Bhagavad Gita(バガヴァッド・ギーター)の一節からの引用です。
このフレーズは原子爆弾の開発者である J. Robert Oppenheimer が核実験後(1945年)に使ったことでより有名になりました。
これは古風な表現ではあるものの現代でも通用しています。
アメリカのドラマで「Heroes」のシーズン3エピソード4(2008年)のタイトルにもなっています。
ちゃんと Wikipedia のページもあります(↓)
では、文法構造をみていきましょう。
become は「~になる」という意味で SVC の文型をとります。
また活用形は become – became – become となります。
「補語 C」は「目的語 O」ではないので「受動態」は機能しません。
それゆえそのまま過去分詞化した become のあとに置いたままになります。

オッペンハイマーによって、”I am become Death” はよく知られる表現とため、英語で検索をかけるといろんなものが見つかります。
【 I am become Death の文法解説(英語)】
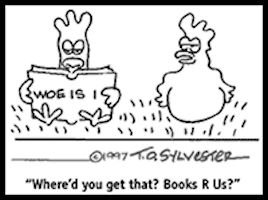
こちらでは完了形をつくるのに be から have に変わった経緯などを解説しています。
このブログを書くのにもたくさん参考にさせて頂きました。
【 I am become Death の元の意味(英語)】
ちょっとここで小ネタに入ります。
オッペンハイマーは「Death 死神」と言っていますが、原典のバガヴァッド・ギータでは「Time 時」と訳すのがより正確なようです。
これは「時の流れの中では万物はいずれ滅び去る」ということで「Time 時」が「世界の破壊者」となるようです。
また英語の「死神」には Reaper / Grim Reaper(命を刈るもの)という言い方もあります。
欧米の「死神」が「(大型の)鎌 scythe」を持つ姿で描写されるのも reap(刈る)からだと思われます。
自動詞の現在完了の例文
現在では自動詞・他動詞など関係なしに「have + 過去分詞」で「完了の動詞」を作れます。
しかし昔は「be動詞 + 自動詞の過去分詞」で完了相を作ることパターンが基本ルールでした。
この経緯を再確認するためブログの冒頭の Wikipedia の記述を引用します。
”This came to be reanalyzed, with the object becoming the object of the main verb, and the participle becoming a dependent of the have verb, as in I have done the work. The construction could then be generalized to be used also with intransitive verbs.”
「ここから文法理解が再分析され、『I have done the work』のように目的語(have の目的語としての the work)が過去分詞(done)を動詞と解釈した場合の目的語(done の目的語としての the work)になり、そして過去分詞(done)は have(動詞)に従属するものとなった。(本来なら be + 過去分詞 で完了を構成するはずの)自動詞でも使われるまでに(have + 過去分詞の)構文が一般化されたと思われる。」
Perfect (grammar) – Wikipedia
昔の用法である SV と SVC の過去分詞を be動詞と組み合わせるパターンは Wikipedia にもいくつか載っていますので紹介します。
SV の完了
- Madam, the Lady Valeria is come to visit you. (The Tragedy of Coriolanus, Shakespeare)
- Pillars are fallen at thy feet… (Marius amid the Ruins of Carthage, Lydia Maria Child)
- I am come in sorrow. (Lord Jim, Conrad)
- I am come in my Father’s name, and ye receive me not (John 5:43, The Bible)
SVC の完了
- Vext the dim sea: I am become a name… (Ulysses, Tennyson)
- I am become Time, destroyer of worlds. (Bhagavad Gita)

最後の例文はバガヴァッド・ギータからですが、オッペンハイマーの訳とは違って「Time 時」になっています。
これは上述した通りで、本来はこちらの意がより適切な英訳として Wikipedia にも載っているのではないでしょうか。
have + 過去分詞のよいところ
さてここまで「have + 過去分詞」が「例外ルール」であることはみてきました。
実際にそんなことまでしてお得なことはあるんでしょうか?
ここからは「私個人の視点」になりますが、プラスなことは「大あり」です。
やはり最大の利点は、他動詞の過去分詞から「受動態」を消し去ることができるからです。
つまり「完了相だけの表現」が生まれます。
そうなると「完了相」を「能動態」で運用できるようになります!!!

日本の英文法ではほぼ無視されていますが「他動詞の過去分詞」には「受動態」と「完了相」の両方がデフォルトでセットされています。
表現によっては「受動態メイン」だったり「完了相メイン」だったり、両方の意味を含んでいたりします。
そこから「have + 過去分詞」を使って「受動態」の無い「完了相」を他動詞の過去分詞にセットできるようになりました。
そうすれば「完了」や「受身」それぞれの意味をより明確に区別して示せるようになります。
では実際に見ていきましょう。
- I have raised him.
- 私は彼を育てあげた(完了相のみ)
- I have him raised.
- 私は彼を育ててもらった(受動態メイン)
上記のように「have + 過去分詞」を使えば「完了オンリー」の意味を示せます。
同時に「過去分詞(単独)」の場合にも「受動態」の意味をより強く示せるようにもなりました。
ただこれは「過去分詞(単独)」が「受動態オンリー」になったわけではありません!!!ここは要注意です!!!
自動詞の過去分詞は形容詞になりつつある
これまで「他動詞の過去分詞」を見てきました。
実は「自動詞の過去分詞」にも「have + 過去分詞」の用法が加わることで変化が起きています。
現代では「 have + 過去分詞(自動詞)」で「完了相の動詞」を表現できます。
さらに「自動詞の過去分詞」には「受動態」はありません。
そもそも「完了相」しかセットされていないので「受動態」と使い分ける理由はありません。
その代わり「品詞」の違いにフォーカスして使い分けがされているようです。
- 自動詞の過去分詞 ⇒ 形容詞
- have + 自動詞の過去分詞 ⇒ 動詞
実際に例文で見ていきましょう。
- The bridge is fallen.
- その橋は = 落ちている(状態)
- The bridge has fallen.
- その橋は落ちた(行動)
自動詞でも「have + 過去分詞」で「完了相の動詞」で運用できます。
それゆえ、「自動詞の過去分詞」は昔より形容詞としての意味が強まり「状態」を示すニュアンスが強くなっていっているようです。
実際に、自動詞 go の過去分詞である “gone” は「もういない、無くなっている、死んでいる」といった意味でよく使われています。
- He has been gone for 10 years.
- 彼は10年間ずっとここにはいない(行方知れず)
この文であれば “has been” で「完了(動詞)」を示し、”gone” で「どっかにいってしまった」という「状態(形容詞)」を組み合わせていると考えられます。
私の勝手な感覚ですが、やはりこちらの意味のほうがメインな気がします。
例外ルールには意味がある
英語の場合は「文の要素 SVOC」と「品詞の使用ルール」が基本ルールになります。
中にはこの have + 過去分詞のように「例外ルール」があります。
でも、それが「間違い」ではなく「例外として認められる」のには理由がある可能性が大きいです。
古い英語では機能していた文法が現代英語で「例外」になってしまっているケースもあります。
歴史を振り返る視点から一度、英文法を見直してみると意外な発見があるはずです。
ちょっとユニークな英語塾
志塾あるま・まーたは英語が苦手が困っている人が、英語を明るく楽しく学べるオンライン英語塾です。
塾長が高校を半年で中退後に、アメリカの大学に4年間留学して習得したゼロから始めて世界で通用する英語力の習得法をみなさまにお伝えしています。
英語の仕組みを正しく見切る「統語論文法 Syntax」を使うので、シンプルなのに素早く、正確に英語が理解できます。
また現代文・小論文の対策なども、アメリカの大学で採用されている論理的思考力や批判的思考力(logical and critical thinking)のトレーニングを基準にして行っています。
あるま・まーたのちょっとユニークな英語の学び方はこちらをご覧ください。
あるま・まーたの英語の学び方に興味を持っていただけたなら、ぜひお問い合わせください!
ブログの感想や英語の疑問・質問などでもお気軽にどうぞ!








