英語の動詞には「世界を動かす4つの力」が秘められています。
- 時を語る力
⇒ 時制 tense - 可能性や願いを示す力
⇒ 法 mood - 動作の進行や完了を描く力
⇒ 相 aspect - そして主語と目的語の関係を操る力
⇒ 態 voice
これらは英語を学んでいれば、一度は目にしたことがある用語だと思います。
ですが学べば学ぶほど・・・
なんで英語の動詞ってこんな仕組みになってんの?
・・・という根本的な疑問が湧いてきませんか?
このブログでは、そうした疑問に対し、文法の本質や歴史的な背景、他言語との比較を通して丁寧に解説していきます。
すでに知っているはずの英語の動詞を、まったく新しい角度から再発見してみましょう!
英語の動詞 verb の多彩な機能
まず英文法用語の「verb 動詞」の語源は「言葉 word」を意味するラテン語の verbum です。
つまり「言葉 verbum =動詞 verb」が言語の中心となる機能をもつ品詞であることを意味します。
なぜなら英語の「動詞 verb」は「行動」を意味し、これが英語の中心になるからです。
- I am here.(~である、いる)
- We have it.(もつ)
英語の be動詞は「動作」というよりも「存在・状況」を意味します。
だから明治の文豪、夏目漱石の有名な作品の英訳もこうなっています
吾輩は猫である ⇒ I am a cat.
英語では「動詞 verb」が「動作 & 存在」も含めて「行動 action」を意味すると解釈してください。
ちなみにドイツ語やオランダ語でも「verb」の別名で「行動の言葉」と呼ぶこともあります。
- ドイツ語 German
- Tätigkeitswort(行動の言葉 / activity word)
- Tunwort(する言葉 / do word)
- オランダ語 Dutch
- Werkwoord(動作の言葉 / work word)
なんだか日本語の感覚と近いのですこし親近感を感じます。
さらに英語の動詞は「行動が起こる時間」を意味する機能も持ちます。
この機能は「時制 tense」といって動詞の形(verb form)で表現できます。
動詞を現在形に変えると「現在時制 present tense」を発動できます。
- I am here.(現在形 am)
- I have it.(現在形 have)
動詞を過去形に変えると「過去時制 past tense」を発動できます。
- I was here.(過去形 was)
- I had it.(過去形 had)
このように「時の言葉」としての役割も「動詞 verb」にはあります。
そのためドイツ語には「Zeitwort = time word(時間の言葉)」という言い方もあります。
またラテン語の verbum にも文法用語としてより明確にするために、あとから temporale(時間の)が追加されることもありました。
- verbum temporale(ラテン語)
- temporal word(英訳:時間の言葉)

このように verb は「行動と時間の言葉」と理解できます。
ここからは日本語にない仕組みですが、主語によって形が変化する仕組みもあります。
- I am here.(1人称単数)
- We are here.(1人称複数)
- You have it.(2人称単数・複数)
- She has it.(3人称単数 )
このように動詞の形をかえて様々な意味を作る仕組みを「動詞パラダイム Verbal Paradigm」といいます。
英語の特徴として、一つの動詞にできることは限られているんです。
そこで英語の動詞は仲間の力を借りてチームプレーを行います。
英語の動詞はチームプレー重視
まず動詞が文の中心的な役割になる動詞として使用されるとき「定形動詞 finite verb」と言います。
これは「主語や時制によって定まる形の動詞」という意味です。
英語などヨーロッパ系言語の基本ルールでは、定形動詞は文の中で1つだけしか使用できません。
日本の英文法では「述語動詞 predicate verb」をよくみます。
ですが、これはラテン語やギリシャ語をベースにした「伝統文法 traditional grammar」の用語です。
この伝統文法で使用される「述語 predicate」では「主語の行動」の解釈に焦点があります。
一方で19世紀後半から「現代文法 modern grammar」のなかで様々な言語理論が登場し始めます。
特に「生成文法 generative grammar」や「依存文法 dependency grammar」は文構造の分析を重視する代表例です。
ヨーロッパ系言語では「定形動詞」が文構造の中心であるため、システム的な分析の核になります。
日本語と違って、ヨーロッパ系言語は「定形動詞 finite verb」を軸に起動させる言語である、という知識は絶対に持っておいて下さい。
ではなぜ英語では「述語動詞」ではなくて「定形動詞」のほうがより大切になるのでしょうか?
それはヨーロッパ系言語のなかでも英語は「1つの動詞の変化パターン」ではなく「複数の動詞の連携」が多く使われる言語だからです。
もし動詞が1つだけなら「述語動詞=定形動詞」になるので、なにも問題ありません。
ですが英語は定形動詞を中心に動詞を連携させるシステムをもつため、動詞の形を変える(定形動詞)だけでは表現に限界があるんです。
まず英語の動詞の連携でユニークな特徴を持つ仲間は大きく2グループあります。
- 法助動詞 modal (auxiliary) verb
- will / can / shall / may / must(現在形グループ)
- would / could / should / might(過去形グループ)
- 非定形動詞(準動詞) nonfinite verb
- to do 不定詞
- doing ING形
- done 過去分詞
では動詞が連携する例をいくつかみていきます。
- I will be here.
- 法助動詞 will
- 動詞 be
- We must have it.
- 法助動詞 must
- 動詞 have
- He is doing it.
- 動詞 is
- 現在分詞 doing
- They have done it.
- 動詞 have
- 過去分詞 done
もちろん3つ同時に連携することもできます。
- I will be doing it.
- 法助動詞 will + 動詞 be + 現在分詞 doing
- They must have done it.
- 法助動詞 must + 動詞 have + 過去分詞 done
1つの動詞だけで表現できることは少ないのですが、仲間によって可能性が広がります。
では動詞の仲間たちのもつ特殊能力を見ていきます。
法助動詞 Modal Auxiliary Verb
日本で一般的に「助動詞」と呼ばれる will や can などは、正確には「法助動詞 modal auxiliary verbs」といいます。
この 「法 mood」とは「話し手の判断や認識を表す方法」を意味します。
ただし、ここで注意すべきは 「助動詞 auxiliary verb」という文法用語そのものの意味です。
本来の「助動詞」とは原形不定詞(do)や分詞(done, doing)を助ける動詞を指します。
つまり現在分詞や過去分詞を助ける be や have も助動詞なんです。
- be 動詞(am / is / are / was / were など)
- have(have / has / had)
これらは primary (auxiliary) verbs(第一助動詞) とも呼ばれます。
- I am doing it.(進行形)
→ 現在分詞 doing を定形動詞 am が助ける。- I have done it.(完了形)
→ 過去分詞 done を定形動詞 have が助ける。
英語と近いフランス語やドイツ語など多くの言語でも、be や have に相当する動詞が分詞を補助する際に「助動詞」と定義されます。
つまりヨーロッパ系言語で「広く一般的に使用される助動詞」なので primary(第一の・主要な)と定義されます。
もちろん、これらは時制や主語に応じて形が変化するため定形動詞です。
つまり、文の中心となりながら、分詞の意味を完成させる役割を持ちます。
さて、次に法助動詞の本体を見てみましょう。
| 法助動詞 | 意味(例) |
|---|---|
| will / would | 意志 |
| can / could | 可能性・能力 |
| may / might | 選択肢・許可 |
| shall / should | 義務・想定 |
| must | 必然性 |
これらは動詞に「話し手の判断・認識」を加える専門の品詞であり、英語の文法書では modal verbs とだけ呼ばれることも多くあります。
なぜなら「古英語 Old English」では法助動詞は、「原形不定詞 bare infinitive」を目的語として取る普通の動詞 だったからです。
この原形不定詞は to をつけずにそのまま動詞の原形を使います。
かつては原形不定詞の基本の意味は名詞用法(=~すること)であり、動詞の「目的語 O」のような位置づけだったんです。
一方ドイツ語では法助動詞は原形不定詞と連携することも単独で動詞として使用することも可能です。
このドイツ語の仕組みは古英語によく似ています。
- Ich kann kommen.(私は来ることができる)
→ I can come.(現代英語と同様)- Ich kann Japanisch.(私は日本語ができる)
→ I “can” Japanese.(英語ではダメ ✖)
ドイツ語では Japanisch(名詞) を目的語に取れます。
これは、普通の動詞にはできることですが、現代英語の法助動詞では不可能です。
また主語によってドイツ語の法助動詞の形が変化するのもポイントです:
- Ich kann Japanisch.(一人称単数)
- Du kannst Japanisch.(二人称単数)
このように、kann / kannst など形を変えるため、まさに定形動詞としての性質を持っています。
現代英語では法助動詞は、形が変化せず固定され、かならず原形不定詞 を後に続けなければ使えません。
これは古英語に存在していた「本来の動詞」としての機能の一部を失っていることを意味します。
それでもなお現代英語の法助動詞は定形動詞として文の中心に立ち、「話し手の判断や認識(mood)」を文に加える重要な役割を果たしています。
- I will be here.
- 法助動詞 will(定形動詞=文の中心)
- 動詞 be(原形不定詞)
- We must have it.
- 法助動詞 must(定形動詞=文の中心)
- 動詞 have(原形不定詞)
英語の助動詞の詳しい解説はこちらをどうぞ。
非定形動詞 Nonfinite Verb
次に非定形動詞は「動詞ではない品詞で使用する動詞」のことです。
日本語では「準動詞」と呼ぶことが多いようですが、英語では nonfinite verb(非定形動詞)と呼ばれています。
英語の表記そのままで「定形ではない動詞」となります。
日本語の「準(≒正式とは言えない)」の意味は「文構造の中心にならない(定形ではない)」となります。
つまり同じ動詞とよばれていても「定形 vs 非定形」で大きく違うので意味を確認してみましょう。
- 定形動詞 finite verb
- 文構造の中心になる機能をもっている
- 主語や時制に対応する形に定まる
- 非定形動詞 nonfinite verb
- 文構造の中心になる機能をもっていない
- 主語や時制に対応する形に定まらない(いつも同じ形)
このことは非定形動詞に「動詞ではない品詞で使用する」という厳しいルールが設定されていることを意味します。
非定形動詞を文法用語で区別する場合は4種類あります。
- 不定詞 infinitive:
- to + 動詞の原形 (to do)
- 原形不定詞もこの仲間
- 動名詞 gerund:
- 動詞のING形 (doing)
- 現在分詞 present participle:
- 動詞のING形 (doing)
- 過去分詞 past participle:
- 動詞の過去分詞形 (done)
同じ「動詞のING形」が「動名詞」と「現在分詞」と違う名前をもっています。
これは昔の英語では2種類の別の形だったものが同じING形になったことに由来します。
- 古英語の動名詞:動詞+ing / ung
- 古英語の現在分詞:動詞+ende
見た目は同じでもそれぞれ設定されている品詞が違うので確認しておきます。
- 動名詞:ING形を名詞としてつかう
- 現在分詞:ING形を形容詞としてつかう
そして非定形動詞は見た目で区別すると3種類になります。
- to do (不定詞)
- doing(動詞のING形)
- done(過去分詞)
見た目は同じでも別々の品詞がセットされているので「文法用語」は変化します。
それぞれ「品詞」ごとの文法用語も確認しておきます。

この非定形動詞を定形動詞を中心とした文に組み込んで使います。
では英語の「文の要素 SVOC」と対応させてみてみます。

非定形動詞は「品詞」が変わると「機能」も変わるのが特徴です。
中でも形容詞として使用する「分詞 participle」には「行動の進行度(相 aspect)」を表現する機能があります。
- 現在分詞 doing:
⇒ 行動が進行している(進行相)- 過去分詞 done:
⇒ 行動が完了した(完了相)
英語の「participle(分詞)」は古典ラテン語の「particeps(共有、参加)」から来ていて、動詞と形容詞の機能を分担、共有することに由来します。
英語以外の言語でも「分詞」は基本的には「動詞の形容詞変化形」を意味します。
フランス語やドイツ語の「分詞」にも使える知識なのでぜひ知っておいてください。
では次に分詞の仲間である「不定詞」を見ていきます。
to と動詞の原形を組みあわせた「to do」の形を持つ不定詞は「~する方向へ」という意味をもちます。
本来は「不定詞 infinitive」は主語や時制によって変化しない「動詞の原形」という意味です。
文法用語は「infinity 無限 ∞」と同じ語源をもつラテン語の infinitivus に由来し「(主語や時制によって)形が限られることの無い品詞」を意味します。
まさに「非定形動詞」の基本形といえるのが「不定詞」なんです。
つまり英語以外の多くの言語では「不定詞」とは「動詞の原形のみ」を示す用語です。
もともと古英語(Old English)の時代は「前置詞 to」と「動詞の原形(名詞用法)」の組み合わせでした。
- 前置詞 to:~の方向へ
- 動詞の原形(名詞用法):~すること
そのため文法用語としては「動詞の原形=不定詞」とするのが正確な定義です。
つまり「原形不定詞 bare infinitive」として残っているものが、実は古英語でよく使われいた不定詞なんです。
しかし現代英語では「to do」をまとめて基本形になっているので「不定詞 = to+動詞の原形」と呼ばれています。
まず現代英語の不定詞は歴史のなかで大きく変化した不定詞の使い方をしている点に注意ください。
さて「不定詞 to do」にはいくつか意味がありますが、その中に「行動をする予定(未然相)」があります。
この「前置詞 to+動詞の原形(名詞用法)」はドイツ語とオランダ語でもよく似た仕組みです。
- to + 動詞の原形(古英語 Old English)
- zu + 動詞の原形(ドイツ語 German)
- te + 動詞の原形(オランダ語 Dutch)
英語、ドイツ語、オランダ語はゲルマン語グループの仲間なので文法にも多くの類似点があります。
もちろん前置詞 to / zu / te を「方向を示す前置詞」として使うのもの共通です。
現代英語と違って、古英語、ドイツ語、オランダ語の「動詞の原形」は基本的に名詞用法です。
実は、動詞の原形が名詞用法なのは、ヨーロッパ系の言語だとほぼ「共通の仕組み」なんです。
これは「to 不定詞」を固定して使わないフランス語、スペイン語、イタリア語でも全く同じです。
しかし現代英語の「動詞の原形」は「命令法」と「仮定法現在」という動詞の「法 mood」を発動させるために使います。
- Be quiet!(命令法を発動する)
- 定形動詞(文構造の中心)
- So be it.(仮定法現在を発動する)
- 定形動詞(文構造の中心)
これらはもともと不定詞とは別の形をしていたのに、英語の歴史の中で同じ形になってしまいました。
つまり英語の動詞の原形は「定形 finite」と「非定形 nonfinite」の2パターンに流用されているんです。
そのため英語の「不定詞(とくに原形不定詞)」と「動詞の原形」の話はかなりややこしいの注意が必要です。
次に「非定形動詞」は「態」とよばれる機能でも重要な役目を果たします。
文法用語の「態 voice」は「行動が『する / される』を区別する」ために使用されます。
受身とよばれる「受動態 passive voice」は、英語では過去分詞だけがもつ機能です。
英語の「態」はのちほど解説いたしますので、カンタンなポイントだけ確認しておきます。
- 能動態:主語と行動の関係が「~する」
- 受動態:主語と行動の関係が「~される」
さきほどの「完了相」と「受動態」を合わせて過去分詞は2つの機能をもちます。
つまり分詞と不定詞は「相 」と「態」の2つの機能を同時発動できます。
- 不定詞 to do:未然相 & 能動態
- 現在分詞 doing:進行相 & 能動態
- 過去分詞 done:完了相 & 受動態
それゆえ不定詞と分詞をみれば、2つの情報を同時に入手できます。
- 行動がどれだけ進んでいるのか?(相 Aspect)
- 行動がするのか?されるのか?(態 Voice)
このように英語の「動詞パラダイム」はユニークな性質をもつ法助動詞と非定形動詞を連携させていろいろな機能を表すことができます。
それが「時制・法・相・態(Tense, Mood, Aspect, Voice)」の4つの機能です。
これらの1つひとつの機能は「文法カテゴリー grammatical category」と呼ばれます。
他の言語も含めれば「文法カテゴリー」はもっとたくさんあります。
しかしこのブログでは英語の動詞パラダイムのもつ機能を中心に扱います。
動詞パラダイムの機能:TMAV
この4つの動詞の機能は「動詞 verb」の基本的なシステムなんです。
さきほどラテン語やドイツ語にはいくつか異なる表現がありましたが、それはヨーロッパ系言語の「動詞 verb」にそれだけ多彩な機能が存在することを意味します。
そのため英語 Wikipedia にもちゃんと書いてあります。
A verb (from Latin verbum ‘word’) is a word that generally conveys an action (bring, read, walk, run, learn), an occurrence (happen, become), or a state of being (be, exist, stand). In the usual description of English, the basic form, with or without the particle to, is the infinitive. In many languages, verbs are inflected (modified in form) to encode tense, aspect, mood, and voice.
動詞(ラテン語 verbum 「言葉」から)は、一般的に 動作(bring, read, walk, run, learn)、出来事(happen, become)、または 状態(be, exist, stand)を表す語である。よくみる英語解説において、動詞の原形(不定詞につく to の有無のどちらの場合も含む)は不定詞とされる。多くの言語では、動詞は 時制(tense)、相(aspect)、法(mood)、態(voice) を表すために形が変化します。
Verb – Wikipedia
ではここから英語の動詞パラダイムがもつ4つの機能(文法カテゴリー)に関連する文法用語を見ていきます。
詳しくは後述するので、用語の確認だけお願いします。
- 時制 Tense
- 話し手から見て行動がいつ起こるものなのか?を表す
- 現在時制 present tense(非過去 non-past)
- 過去時制 past tense
- ✖ 未来時制(厳密には英語は未来時制を持たない)
- 話し手から見て行動がいつ起こるものなのか?を表す
- 法 Mood
- 話し手の判断・認識を表す
- 直説法 indicative mood
- 仮定法(接続法)subjunctive mood
- 命令法 imperative mood
- 法助動詞(いろいろな「法 mood」を発動可能)
- 話し手の判断・認識を表す
- 相 Aspect
- 行動の実現度を表す
- 未然相 prospective aspect
- 進行相 progressive aspect
- 完了相 perfect aspect
- 行動の実現度を表す
- 態 Voice
- 主語と行動の関係が「する / される」を区別する
- 能動態 active voice
- 受動態 passive voice
- 主語と行動の関係が「する / される」を区別する
ところで日本の英文法解説で「時制・法・相・態(TMAV)」をしっかりと習った方は少数ではないでしょうか?
その理由は一般的な日本の英文法書だと別々の見出しになっているからです。
そのため「同じ形がある」のに「バラバラの用語」がつけられたりします。
- I am going to school. 現在進行形
- I am going to do it. 未来形
- Your window has broken. 現在完了形
- Your window is broken. 受動態
- Be nice to her. 命令文
- Be that as it may,… 仮定法現在
- You were there. 過去時制
- I wish I were there. 仮定法過去
- If it were to happen tomorrow,… 仮定法未来
これでは「英文法の意味が分からない!」となってしまうのも納得です。
ですがご心配なく!
英語はちょっと視点をかえるだけで一気にわかりやすくなります。
分析的言語 & 統語論(Syntax)
英語は単語同士を組み合わせて意味を表すタイプの言語です。
このような言語を「分析的言語 analytic language」といいます。
一方で、1つの単語をいろいろ変化させて意味を表すタイプの言語も存在しています。
そのような言語を「総合的言語 synthetic language」といいます。
この2つの特徴を英語の「未来形」とよばれる be going to に当てはめてみます。
- I am going to do it.(英語・分析的)
- 私は それを するつもりです。(日本語・総合的)
英語は4つの単語のチームプレーですが、日本語は「動詞の形」が変わります。
また英語の「未来完了」と呼ばれる連携をフランス語やラテン語と比べてみます。

ほぼ同じ意味なのに英語は3連携、フランス語は2連携そしてラテン語は1つの動詞です。
ラテン語に至っては「主語の情報 we(一人称複数)」まで動詞を変化させて対応できます(主語が省略可能な場合も多い)
ではこの2タイプの言語の特徴をまとめてみます。

このように言語のタイプによって有効な学習法が変わってきます。
- 分析的言語 analytic language:
- 単語同士のチームプレーの仕組みを見切る!
- 総合的言語 synthetic language:
- 1つの単語の変化パターンを見切る!
自分が学びたい言語がどのようなタイプなのか知っておくと学習効率が上がります。

現代英語はヨーロッパ系言語のなかでも「分析的 analytic」な性質が強いことがお判りいただけると思います。
では先ほどの be going to を「分析的言語」の視点から分解してみると・・・・
- am:be動詞(直説法・現在時制)
- 定形動詞(文の中心)
- going:現在分詞(進行相)
- 非定形動詞
- to do:不定詞(未然相)
- 非定形動詞
これを英語の語順で当てはめてみると・・・
- I am going to do it.
- 私は 現在~である 向かっている する方向へ それを。
・・・といったように理解することができます。
現代英語は分析的言語なのに比べて、日本語は総合的言語なのでそれぞれ仕組みが大きく違います。
そのため和訳は英語と同じように機能してくれないことが多くあります。
そこで「英単語のチームプレーの仕組み」を重視した理解をすることで、英語を正確に自由自在に運用できるようになります。
この「単語同士のチームプレーの仕組み」を重視した文法を「統語論 Syntax」といいます。
まず「文法 grammar」の基本を確認します。

現代英語で特に重要になるのが「統語論」と「意味論」をうまく組み合わせて利用することです。
- 統語論 Syntax:
- ルール・システム重視の文法解釈
- 語順や連携の構造を理解するのに有効
- 意味論 Semantics:
- 意味・ニュアンス重視の文法解釈
- 例外や熟語も含めて理解するのに有効
この「統語論」は単語の並べ方や連携の仕組みをシステム的に理解することを重視します。
つまり現代英語は「分析的言語」なので「統語論」の分析がかなり有効なんです!
英語を学ぶときに重要なことは「動詞パラダイム」の仕組みを統語論と意味論の2つの視点から見ることです。
ではなぜ「統語論 syntax」の視点での分析をあまり目にしないのでしょうか?
それは冒頭で述べた「伝統文法 traditional grammar」に要因があります。
現代文法は「述語動詞」を分析する
伝統文法の特徴は「述語動詞」というひとまとめの解釈をとります。
英文解説で「動詞 V」だけとんでもなく長い解説をみたことがありませんか?
- You might be going to have to be able to speak English.
- あなたは英語を話せるようにならないといけなくなるかもしれませんよ。
⇒ SVO の第3文型!(え?そんなムチャいわんといて!)
この解釈では主語と目的語までがまとまってひとつの「述語動詞」になってしまいます。
ですが英語は「動詞の連携」によって様々な意味をあらわすのでこれでは困ります。
そのため現代文法には動詞の連携を分析する理論がちゃんとあります。
- 生成文法 generative grammar(GG)
- 文全体を「名詞句(フレーズ)」と「動詞句(フレーズ)」の2つから成立すると考える
- 述語動詞のまとまりが「定形動詞からの連携(動詞句)」として分析される
- 依存文法 dependency grammar(DG)
- 他のすべての要素が定形動詞に依存する(depend)構造としてとらえる。
- 文の中心構造が定形動詞なので「主語&述語」という解釈をしない。
ちなみにChatGPTが文構造を分析する attention mapping という仕組みは「依存文法」によく似ているんです。
これらの手法だと定形動詞を中心に統語論で分析するため「述語動詞の丸暗記」をしなくてもいいんです。
では実際に「伝統文法」と「現代文法」で動詞の連携を比べてみます。

このように伝統文法の述語動詞にたいして「統語論 syntax」と「意味論 semantics」から2つの解釈で分析が可能です。
ではこんがらがりやすい3つの「動詞」をまず整理しておきます。
- 本動詞 main verb
- 定形動詞 finite verb
- 述語動詞 predicate verb
これらは動詞が一つしかない場合はすべて同じです。
しかし動詞の連携(動詞句)の分析では違うものになるので、混乱しないように注意して下さい。

ではここから「時制・法・相・態(TMAV)」の4つが機能するカラクリに進んでいきます。
① 時制 テンス Tense
文法用語の「時制 tense」とは話し手から見て「行動がいつ起こったか?」を表します。
英語の「tense」は、ラテン語の「時」を意味する tempus から古フランス語の tens を経て「時制」を意味する英単語になりました。
- 現在時制 present tense
- 過去時制 past tense
- ✖ 未来時制 future tense
⇒ 英語には未来時制ないんです
英語の時制は「動詞」や「法助動詞」を変化させて発動するため「定形動詞 finite verb」の機能です。
言い換えれば、時制を表現するための「動詞の形 verb form」が必要になります。
英語の動詞が時制を表すには「現在形 present form」と「過去形 past form」しかありません。
また「動詞の原形 base form」は「主語と時制に関係なく使う(いつも原形になる)」ので時制は表現できません。
- am / are / is
⇒ be動詞の現在形(present form)- was / were
⇒ be動詞の過去形(past form)- be
⇒ be動詞の原形(base form)
つまり英語の動詞は未来形に変化しないので、英語には未来時制は存在しません。
同じく法助動詞も元々は動詞だったので定形動詞として「現在形」と「過去形」を持ちます
- will / shall / can / may / must(現在形)
- would / should / could / might(過去形)
注意点として現代英語の法助動詞は『「時制 tense」よりも「法 mood」の機能が強化』されています。
そのため「法助動詞の過去形」は現在時制でも使用可能になっています。
- Would you help us, please?
- 我々を手伝ってくれませんか?お願いします。
- He could be around here.
- 彼はこのあたりにいる可能性がある。
英語の時制は「非過去」と「過去」
英語の時制は2つしかないので「現在 present」は未来表現も担当します。
そのため英語の現在時制はより正確には「非過去 non-past」と呼ばれます。
- 非過去時制(現在~未来):
- まだ行動できる時間(今から行動可能)
- 過去時制(過去):
- もう行動できない時間(今では行動不可能)
よく英語で「未来時制(未来形)」と呼ばれるものは中身は「非過去時制(現在時制)」です。
- I will do it.
- 法助動詞の現在形 will を使用
- I am going to do it.
- be動詞の現在形 am を使用
この「非過去 & 過去」の2時制システムは英語・ドイツ語・オランダ語といったゲルマン語の特徴です。
そのためドイツ語とオランダ語にもホンモノの「未来時制」は存在しません。
実際にドイツ語では未来のことでも現在時制(非過去)で表現することは頻繁にあります。
さて、この2つの時制は「古英語 Old English」から現代英語にも受け継がれています。
英語の時制に「非過去(現在~未来)」を組み込むだけでとてもスムーズに機能します。

図のように「非過去(まだ動く)」と「過去(もう動かない)」の2つの区分は、時制だけではなく「相 aspect」にも発動します。
この「相」とは「行動の進行度」を表す文法用語で「時制」とは別の機能になります。
つまり「現在」と「過去」は動詞と分詞(動詞の形容詞変化形)にそれぞれ別の形で関係してきます。
- 動詞(時制を表す)⇒ 定形動詞の専用機能
- 現在時制(非過去時制 non-past tense)
- 過去時制(過去時制 past tense)
- 分詞(相を表す)⇒ 品詞は形容詞(非定形動詞)
- 現在分詞(進行相 progressive aspect)
- 過去分詞(完了相 perfect aspect)
時制と相の違いは後述の「相 アスペクト aspect」で説明させていただきます。
ここではまず『英文法の「現在 presnt」と「過去 past」は時間だけの話ではない!』と頭に叩き込んでください。
では話を「時制」に戻します。
なんとラッキーなことに日本語も「非過去 & 過去」の2時制システムと相性がいいです。
- 未来:明日○○する(非過去)
- 現在:今日○○する(非過去)
- 過去:昨日○○した(過去)
英語は「非過去(行動できる)& 過去(行動できない)」の理解のほうが、日本語とうまく連動します。
ちなみに「未来時制」はラテン語やその子孫のフランス語やスペイン語などに存在します。
これら「ロマンス語 Romance Languages」と呼ばれる言語グループでは、動詞が未来形に変化するので、正真正銘の「未来時制 future tense」があります。
ヨーロッパ系の言語を学ぶ時は「動詞の形(つまり定形動詞)」をみて時制を理解することが重要です。
あくまでざっくりですがこんなイメージで分けられます。
- ゲルマン語:2時制システム
- 非過去 non-past
- 過去 past
- ロマンス語:3時制システム
- 未来 future
- 現在 present
- 過去 past(英語の過去時制とすこし違うので注意)
本当はロマンス語の時制はもっと細かいのですが、ここでは大枠をつかんでください。
英語の未来時制の考え方についてはこちらのブログをご覧ください。
さて英語と日本語の動詞は2時制システムをとるので「現在=非過去」の理解が便利です。
英文法で「現在時制 present tense」をみたら「非過去時制(現在~未来)」と頭の中で切り替えてください。
このブログでは一般的な表現を優先して「現在時制」と書くことも多々ありますが、英語やドイツ語などゲルマン語グループの場合は「非過去時制」と同じ意味になります。
② 法 ムード Mood
文法用語の「法 mood」は「話し手の判断・認識」を表します。
英文法用語の「mood」はラテン語で「方法・手段」を意味をする modus(英語 mode)から派生して生まれました。
ときおり「話法(もしくは叙法)」とよばれることもあるので「話し手の判断・認識を伝える方法」という理解が一番良いと思います。
では英語の動詞が発動可能な3種類の「法 mood」を見ていきます。
- 直説法 indicative mood
- 仮定法(接続法)subjunctive mood
- 命令法 imperative mood
直説法 Indicative Mood
直説法(indicative mood)とは、話し手が「事実であると判断・認識すること」を表現する文法用語です。
英語の indicative の由来はラテン語の indicativus で「(事実という)認識を示す」という意味になります。
日本ではわかりやすいように「事実モード」という説明をされることもあります。
注意点としては、あくまで「話し手の判断・認識」なので、実際に事実かどうかは断定できません。
それゆえ「(話し手が)事実(と考えている)モード」であることを忘れないでください。
そして直説法とは、いわゆる普通の現在時制と過去時制のことです。
- I am here.
- 現在時制 直説法 present indicative
- I was here.
- 過去時制 直説法 past indicative
基本的に英語の「法」は動詞を「法に対応する専用形」に変化させることで発動します。
つまりこの「法」の発動も「定形動詞」が担当する機能です。
実は英語の動詞は「時制 tense」と「法 mood」を同時に発動しているんです。
中学で “He talks a lot.” の動詞 talk の変化形 talks を「三単現の s」と習うかと思います。
実際にはこれは「三単現直」がより正確な表現です。
- △ 三人称単数現在(通称:三単現)
- 〇 三人称・単数・現在時制・直説法
動詞が「時制」と「法」を同時に発動する仕組みはドイツ語やフランス語などでも全く同じで、定形動詞が担当します。
そして直説法と同じシステムが「仮定法(接続法)」にも組み込まれています。
仮定法・接続法 Subjunctive Mood
仮定法(subjunctive mood)とは、話し手が「事実ではなく想定・推測だと判断・認識すること」を表現する文法用語です。
それゆえ直説法の「事実モード」と対比させて「想像モード」と呼ばれることもあります。
直説法と同じく、動詞の形を仮定法専用形に変化させれば発動することが可能です。
英語の文法用語 subjunctive はラテン語の subjunctivus に由来し、「下 sub + つなげる join(従属させる ≒ subordinate)」という意味から派生しています。
このラテン語の subjunctivus は、ギリシャ語の「hupotaktike ≒ 下に整列させる」の翻訳です。
ギリシャ語の文法が「想定・推測を表す動詞の形は従属節(主節に接続する文)の中で使用する」という構造をしていたことが由来です。
そのためドイツ語やフランス語など英語以外の文法書は「接続法 subjunctive mood」と呼んでいます。
実際にヨーロッパ系言語の「接続法」の用語を見ていきましょう。
- subjunctivus(ラテン語 Latin)
- subjunctive(英語 English)
- Konjunktiv(ドイツ語 German)
- conjunctief(オランダ語 Dutch)
- subjonctif(フランス語 French)
- subjuntivo(スペイン語 Spanish)
- congiuntivo(イタリア語 Italian)
すべてラテン語(翻訳元はギリシャ語)に由来するので「junct(つなぐ)」の意味が入っています。
しかし「接続法」と呼ばれてはいますが、実際には「想定・推測」が本来の役割なので、主文でも普通に使います。
それぞれの言語で subjunctive の使用方法に大きな差がありますが「想定・推測を表すための動詞の形」という点では共通です。
ところが日本の subjunctive の翻訳語はバラバラで、私の知るだけでも4つもあります。
- 仮定法
- 叙想法
- 仮想法
- 接続法
これに加えて、時には「条件法」というものも混同されて使われています。
しかし「条件法 conditional mood」は subjunctive mood とは別の機能を意味していて、英文法での必要性は限りなくゼロに近い用語です。
なぜなら条件法はフランス語やスペイン語などロマンス語グループで使用する用語なんです。
英語やドイツ語の動詞に「条件法専用形」は昔から今までずっと存在しないので注意してください。
日本の英文法解説では、英語 subjunctive にいくつも和訳があり、さらに conditional までまぜこぜですから、みんながバラバラなことを言っているようにみえます。
しかし「仮定法」や「叙想法」などの違いは和訳だけの問題なので全く気にする必要はありません。
英語の「subjunctive」の語源はラテン語の「接続法 subjunctivus」であり、これはヨーロッパ言語で共通です。
それゆえ「話し手の想定・推測を接続して伝える方法」という知識さえあれば何も問題ありません。
とはいえ日本の英文法用語の残念な現状にあわせて、ここからは「仮定法(英語以外では接続法)」と表記します。
英語の仮定法とは「動詞の形」で表す「法 mood」なので、直説法と同じように「時制」と同時発動させて扱います。
- 仮定法現在 present subjunctive
⇒(仮定法 x 現在時制)- 仮定法過去 past subjunctive
⇒(仮定法 x 過去時制)
ところが現代英語では仮定法の形は使用するところが限定されています。
古英語の時代には仮定法専用形がそれぞれの動詞に存在したのですが、現代英語では直説法と同じ形になってしまいました。
一方、現代のドイツ語やフランス語では動詞の「接続法専用形」はそれぞれタイプは大きく違いますが普通に使用するものです。
まず現代英語の仮定法が分かりにくい理由は「仮定法専用形がほぼ消えてしまった」からです。
唯一の例外は be動詞なので「時制」と「法」を同時に確認します。

ここで注意ですが be動詞にも「仮定法専用形」はありません。
仮定法過去 were は直説法過去 were と同じ形です。
同じく「動詞の原形」も複数の機能を発動可能な形で「定形」と「非定形」の2パターンあります。
- 動詞の原形が「定形 finite」とされる
- 命令法
- 仮定法現在
- 動詞の原形が「非定形 nonfinite」とされる
- to 不定詞 “to be”
- 原形不定詞 “will be” “let it be”
このように見た目だけでは「動詞の原形」の機能と意味は分かりません。
あくまで「be動詞は仮定法の発動がわかりやすい時がある」とご理解ください。
さて仮定法は「想定・推測」を伝えるので「現実世界 real world」の話はできなくなります。
その代わり「想像世界」の話をすることができます。
- 直説法:現実世界
- 話し手が事実として認識すること
- 仮定法:想像世界
- 話し手が想定・推測として認識すること
英語ではこの仮定法(想像世界)に「時制 tense」を組み合わせて考えます。
おさらいになりますが英語(ゲルマン語グループ)の「現在時制」は「非過去(現在~未来)」です。
- 非過去時制 non-past
- 今から行動できる時間(現在~未来)
- 過去時制 past
- 今では行動できない時間(過去)
想像世界は「時制」に「事実モード」が適用できません。
なぜなら「想像モード」が発動するので「すべて想定・推測になってしまう」からです。
そのため「仮定法」を2つの時制と組み合わせると、次のようになります。
- 仮定法現在(非過去)
- まだ起こりそうだと判断・認識すること
- 仮定法過去
- もう起こりそうにないと判断・認識すること
これを直説法と一緒にまとめます。
- 直説法現在:事実モード & 行動できる
- ⇒ 現在~未来の事実となること
- 直説法過去:事実モード & 行動できない
- ⇒ もう決まってしまった事実であること
- 仮定法現在:想像モード & 行動できる
- ⇒ まだ事実になる可能性があると思う
- 仮定法過去:想像モード & 行動できない
- ⇒ もう事実になる可能性はないと思う
では表で確認してみます。

このように「時制 tense」と「法 mood」は合計4種類の情報を動詞の形で表しています。
日本では未来時制や仮定法だけを分離した解説もよくありますが、英語も含めてヨーロッパ系の言語は本来そういうシステムではありません。
仮定法(接続法)の本質は「話し手は起こりうる可能性を伝えたいんだ!」と理解することです。
ところが日本の仮定法の解説では、現代英語の仮定法過去形だけを切り取ったものが圧倒的過半数なので、悲惨な状況になっています。
ドイツ語やフランス語の基本を学ぶだけで「時制 tense」と「法 mood」の考え方がしっかりわかります。
ですが日本の現代英語の文法書だけで、これらを理解するのはかなり難しいかもしれません。
なによりも「現代英語では仮定法専用形が無くなってきている」という前提が存在します。
そのため現実問題として仮定法は現代英語の例文を見てもよくわからないんです。
そこで基本に立ち返るため「古英語 Old English」を参考に進めていきます。
古英語の仮定法は主に次の3つで使用します。
- 義務・要求・想定・願望などを意味する動詞・形容詞からつながる文の中の動詞
- 願望・希望などを意味する動詞
- 時・条件文の中の動詞
古英語の仮定法(接続法)については英語 Wikipedia を参照ください。
仮定法現在(接続法非過去)
ここから「仮定法現在 present subjunctive」に入るので、まず文法用語の確認です。
- 仮定法:想像モード
- 現在時制(非過去):行動可能な時間
この2つを組みあわせて考えると・・・
- 仮定法現在(非過去)
- まだこれから起こりそうと思う
- (行動できる+想像モード)
現代英語では仮定法現在は標準用法としてつかわなくなっています。
それでも古英語の仮定法の使用パターンがのこっているので見ていきましょう。
では「仮定法現在」の例文を確認します。
現代英語でも suggest や insist などの「提案・命令・要求・依頼」の動詞からつながる that 節では仮定法現在(動詞の原形)を使用します。
I have to insist that you be more specific.
『私はあなたがもっとはっきりしてくれるように要求せざるを得ない。』
動詞だけでなく「命令・要求」などの形容詞からつながる that 節でも「仮定法現在」を使います。
It was necessary that everyone be able to do it.
『みんながそれをできることが必要であった。』
またフランス語でもこの2タイプの文章で que 節(英語の that 節)で使用する動詞を「接続法 subjonctif」に変化させて使用します。
このような英語の仮定法現在が必要になる動詞や形容詞はフランス語の接続法がほぼ網羅しています。
もちろんフランス語の接続法は英語よりも、はるかに使用範囲は広いので注意してください。
私がフランス語学習でお世話になっている Lawless French さんのサイトをぜひ参考にしてみてください。
ところが日本でよく見るこの2タイプの解説では「should の省略」が多数派かと思います。
実は「仮定法現在を示す動詞の原形の前に、イギリス英語で法助動詞 should が追加された」というのが正しい英語の歴史です。
つまりアメリカ英語のほうに英語の本来の用法が残されているということなんです。
またカナダのケベック州のフランス語も同じような特徴があり、フランス人から見れば古風な表現がカナダのフランス語には残っているそうです(フランス文学専攻のカナダ人に聞きました)
では次に「祈願文 request」に進みます。
この形でも「仮定法現在」の形が使用されます。
- God bless America!
- アメリカに God の祝福があらんことを!
さて God(代名詞は He)は3人称単数なので直説法現在の動詞は blesses です。
この用法は、英語のゲルマン祖語の段階で「祈願法 optative mood」という形が「仮定法現在」に取り込まれたことが由来です。
ちなみにみなさんよくご存じ “goodbye” も祈願法(仮定法現在)に由来します。
- God be with you. ⇒ goodbye
- God があなたと共にあらんことを!
- 仮定法現在 be(祈願法 optative)
もともと英語の最も古いご先祖様とされる「インド・ヨーロッパ祖語 Proto-Indo-European Language(略語 PIE)」では4種類の「法」があったとされています(いまのところ仮説)。
- 直説法
- 仮定法・接続法
- 命令法
- 祈願法 ⇒ 仮定法・接続法に取り込まれる(ゲルマン祖語の時代)
こういう経緯があるので、英語と同じゲルマン語のドイツ語などでも「祈願」の表現は、英語の「仮定法現在」と同じ仕組みをもちます。
正確に言うとドイツ語文法は「仮定法現在」ではなく「接続法 I 式 Konjunktiv I」と呼んでいますが、中身はほぼ同じものです。
ただ現代英語では「祈願の仮定法現在」に法助動詞 may を追加するケースが一般的です。
- (May) fortune be with you!
- 幸運があなたと共にありますように!
さらに法助動詞 may だけでなく動詞 let も同じような意味で使えます。
- May the best man win!
- 最高の結果を出した者が勝ちますように!
- ⇒ 正々堂々と戦おう / 恨みっこなしだ
- Let the best man win!
- 最高の結果を出した者を勝たせてあげて!
動詞 let をつかった表現の文構造は「命令法」になっています。
命令法と仮定法現在はどちらも「動詞の原形 base form」を使います。
この2つが同じように使える理由は「命令法 imperative mood」のところで後述します。
英語の仮定法現在はシェイクスピア(1564 – 1616)の時代の「初期近代英語」までは標準用法で、たくさん使われていました。
そのため昔よく使われていた仮定法現在は定型表現として残っています。
- So be it.
- 分かりやすくすると ⇒ It be so.
- 『(もしそれがそうなりそうなら・・)それはそのようにあれ。』
- ⇒ そうなるならそれでよい。
- Be that as it may, SV.
- 分かりやすくすると ⇒ (If) that be as it may (be), SV.
- 『もしそれがなりうるように、実際にそうなったとしても…』
- ⇒ たとえそうであったとしてもそれと関係なく…
- Come what may.
- 分かりやすくすると ⇒ What may (come), come.
- 『起こりうることが起こってしまってよい。』
- ⇒ これから何が起きようとも…(私は動じない)
上記の表現は日本の文法書でもよくみますが「仮定法現在」に分類されないケースも多いようです。
ではここから「条件文 if SV」でつかう仮定法現在を見ていきます。
少し古い英語までは「時・条件を表す副詞節」でも「仮定法現在」を使用することもありました。
この条件節でつかう仮定法現在(接続法現在)はフランス語にはありません。
同じ仮定法現在でも動詞・形容詞からつながる仮定法現在(フランス語にある)と条件節に登場する仮定法現在(古英語にある)が混在しているので注意下さい。
現代英語の用法と合わせて確認してみます。
- If it is sunny tomorrow, I will go hiking.(直説法・現在時制)
- If it be sunny tomorrow, I will go hiking.(仮定法・現在時制)
これらは受験英語の参考書などに「時・条件を表す副詞節では未来のことでも現在形を使う」という解説とは少し違います。
そもそも「未来」は不確定な話なので、話し手の判断で「仮定法」をつかうことも可能でした。
そもそも「未来=will」という視点ではなく、現在形の動詞が「非過去時制(未来も対応可能)」を意味する英語では「法」の切り替えを行っていました。
- 現代英語:直説法現在形
- 昔の英語:直説法現在形もしくは仮定法現在形
日本でよくみる英文法解説は「時制 x 法」の仕組みが欠落しているものがよくあります。
そこで「時制」と「法」を区別して解説をやり直してみます。
このパターンの場合は法助動詞 should や may の追加ではなく「直説法だけ」になりました。
そのため動詞の原形が消えてしまったので、もともとの仮定法現在の存在がほぼわからなくなってしまいました。
とはいえ現代英語でも文語体や堅い文章などでまだ仮定法現在形を使うことがあります。
ではシェイクスピアの例文をみてみましょう。
If music be the food of love, play on.
『もし音楽が恋の糧であるならば、奏で続けよ。』
Shakespeare, Twelfth Night, Act 1, Scene 1
英語の歴史も踏まえると「動詞の原形」は「命令法」や「不定詞」の専用パターンではないんです。
英語の動詞を「時制 x 法」でとらえることで、すこし古い英語でもちゃんと理解できます。
まず落ち着いて動詞の形をみて TMAV の理解に切り替えてみましょう。
ただ現代英語では仮定法現在を使うことは限定されつつあるので、これ以上は深入りはしないようにいたします。
仮定法過去(接続法過去)
では次に「仮定法過去 past subjuctive」です。
もう一度、文法用語の確認です。
- 仮定法:想像モード
- 過去時制:行動不可能な時間
この2つを組みあわせて考えます。
- 仮定法過去
- もう起こりそうにないと思う
- (行動不可能+想像モード)
そのため次のような意味を表現することができます。
- 事実とは異なること(反事実 counterfactual)
- 確信度の低い推測
- 実現しそうにない願望
現代英語の仮定法過去形は be動詞以外は直説法過去形と同じ形にまとまりました。
そこで例文はわかりやすいように be動詞の仮定法過去形 were を使います。
- I wish I were there.
- 私がそこにいることができればと願う(けどムリやねん!)
現代英語では動詞 wish は仮定法過去の形をつなげるほぼ唯一のパターンの動詞だと思います。
古い英語ではホンモノの動詞 would も使いますが、とりあえず wish を知っておけば何とかなるはずです。
そして仮定法過去の最大の見せ場と言えば「反事実条件 counterfactual conditional」です。
- If I were there, I would be dead by now.
- もし私がそこにいたら、いまごろ死んでいただろう(まあ実際はそこにおらんかったけど)
日本の参考書でよくみる「仮定法」は次のような構造をしています。
- if の文 :事実とは異なる条件をつくる(動詞は仮定法過去形)
- 主文 :条件に合わせて、話し手の意見を述べる(法助動詞 would の過去形)
実は「仮定法過去」は「もし○○だったら、~だろう」のような文でなくても使用可能です。
話し手が「事実として伝えるのは適切ではない」という意図で使うこともよくあります。
- She tells a lie as if it were true.
- 彼女はウソを言う、まるでそれが真実であるかのように(まあホントなわけないやろけど)。
ほかにはイディオムとして丸暗記しがちなところにも仮定法過去が登場します。
- as it was:実際に○○だったように
- as it were:実際にはそうではないが、○○であるように(≒ いわばまるで)
あくまでも仮定法は「話し手の想定・推測」を伝える動詞の形です。
- 事実ではないのはわかっているけど、もしそうだったらという話ね
- 事実であることはありえないと考えてるけどね
- 事実かどうかよくわからない前提で言ってるんだけどね
このような話し手の判断・認識を仮定法過去形から受け取ってください。
さらに仮定法未来と呼ばれることもある「if S were to do」も実は「仮定法過去」です。
- If it were to happen tomorrow, what would I do?
- もし万が一、それが明日起こるなら、私はどうすればいいだろう?
構造はシンプルで「be動詞 + 不定詞 to do」なので「~する方向へ(未然相)」を作っています。
英文法書で「be to 構文」と呼ばれている形の be動詞を仮定法過去にしただけです。
近代英語までは、未来を想定するケースで、今後どうなるかは不明なときは「仮定法現在」で表現することがよくありました。
しかし話し手が「そんな未来は起こらないだろう」と強く思う場合、仮定法過去を使います。
- If S were to do, ~.
- 和訳:もし万が一○○するなら…、もしあえて○○するとしたら…
- 話し手の意図:○○する方向に向かう可能性はほぼないと判断している
このように仮定法過去 were を使ったことで「未来に起こる可能性」に否定的な認識を表現できます。
それゆえ話し手が「起こりそう VS 起こらなそう」を切り替えて表現できます。
- もし明日晴れるなら・・・
- If it be sunny tomorrow, ~.
- 晴れそう ≒ 仮定法現在
- If it were to be sunny tomorrow, ~.
- 晴れなさそう ≒ 仮定法過去+未然相
このような仮定法の使い分けは現代英語ではしなくなりつつありますが、カラクリを知っておくと古風な英文にも対応できます。
仮定法をうまく使えば「未来に起こる可能性」について「肯定的 or 否定的」の2つから選択できます。
反事実条件と仮定法
日本の英語学習では「反事実条件」と「仮定法」がごちゃごちゃになる解説をよく見ます。
- 仮定法(接続法)subjunctive mood
- 話し手の想定・推測を伝えるための動詞の形
- 反事実条件 counterfactual conditional:
- 事実とは異なる条件と、その結果を想定・推測する文
日本の英文法書でこれらを明確に区別している解説を見つけるのは難しいと思われます。
受験やTOEICを対象とした解説のレベルでは、これらが判別できなくなるのはムリもありません。
実際のところ仮定法(接続法)は言語によって使用法が大きく異なり、古英語と現代英語ですら大きく違います。
そのため英語圏でも subjunctive の解説はバラついていて、それには言語の特徴や歴史が関係しています。
現代英語で一番ややこしいのは「法助動詞の過去形」の使い方です。
これが英語の歴史の中で仮定法に置き換える形でどんどん使われたので、文法書の例文が意味不明にしかみえなくなってしまっています。
一方で現代ドイツ語は古英語とよく似た文法構造をいまでも持っています。
そのため「接続法Ⅱ式 Konjunctiv II」という動詞の形を反事実条件文で使います。
このドイツ語の「接続法 konjunktiv」が昔の英語の「仮定法 subjunctive」に対応します。
- 仮定法現在(英)≒ 接続法Ⅰ式(独)
- 仮定法過去(英)≒ 接続法Ⅱ式(独)
ところが現代英語では「仮定法の動詞の形」が消えつつあり、「反事実」と「仮定法」を分離して考える必要性が大きくなっています。
この反事実条件文に「直説法過去」をつかうのはフランス語なども同じで、現代英語がムチャなことをやっているわけではありません。
あくまで「直説法過去形」を「絶対に事実モードだ!」と決められなくなっているんです。
それでは本来なら仮定法過去形 were を使用する位置に直説法過去形 was を使うケースを見ていきます。
- I wish I was more helpful.
- もっとお役に立てればよかったのですが(実際はそうではない)
これに加えて、仮定法現在にも法助動詞 should や may を追加する傾向もあります。
つまり現代英語では直説法や法助動詞が仮定法の役割を吸収している流れが存在します。
そうなると現代英語だけをみて「仮定法はこうだ!」とカンタンに説明できるわけがないんです。
仮定法(接続法)は英語やほかの言語の歴史の流れを追うことでやっと本来の姿が朧気ながら見えてくるものなんです。
このあたりの「反事実条件文」の考え方は英語 Wikipedia に詳しく載っています。
命令法 Imperative Mood
ではここから「命令法 imperative mood」に進みます。
英語の imperative の由来はラテン語で「命令・指令・要求」を意味する imperativus です。
一般的に文法用語としての「命令法」は「2人称 you に要求する行動」のことです。
もともと古英語には「命令法」を発動する動詞の専用形が存在していました。
たとえば動詞 sing は古英語ではこのような変化パターンをもっていました。
- singan(動詞の原形)
- singe(直説法現在時制:一人称単数)
- sing(命令法:二人称単数)
- singaþ(命令法:二人称複数)
見たことがない文字が古英語にある理由は、古英語の時代はアルファベットではなく「ルーン文字」が使用されていたからです。
古英語の動詞の変化パターンはこちらのサイトに解説があります。
現代英語では主語を「二人称 you(通常は省略)」にして「動詞の原形」で「命令法」を発動させます。
注意点としては「動詞の原形」であっても「命令法を発動する定形動詞」ということを忘れないで下さい。
時制について言うと「命令法・現在時制」としての扱いも可能ですが、対応する過去形がないので時制の切り替えはできません。
- Be quiet. (≒ You be quiet.)
- 静かにしなさい.
そもそも命令法は、話し手 “I” から 聞き手 “you” への会話として成り立ちます。
そのため強調のために「二人称の主語 you」をつかうこともあります。
- You stay here, ok?(命令法)
- 君はここにいろ、わかったな?
ところが主語が3人称になると「文法用語」が変わる場合があります。
その場合「仮定法現在(祈願)」と呼ばれます。
- God bless America!(仮定法現在)
- 〇 God がアメリカを祝福されんことを(私は願う)!
- ✖ God はアメリカを祝福せよ!
これは先ほど「仮定法現在」のところでお話した「祈願法 optative mood」を取り込んだ形です。
そのためドイツ語の接続法第 I 式(仮定法現在)にもほぼ同じ用法があります。
ドイツ語の動詞 helfen(≒ 英語 help)で比べてみます。
- Hilf mir!(≒ Help me!)
- 命令法(2人称)
- Gott hilft dir. (≒ God helps you.)
- 直説法現在形
- Gott helfe dir. (≒ God help you.)
- 接続法第 I 式(祈願を示す)
どれも helfen(動詞の原形)とは違う形なので、ドイツ語の命令法(2人称)と接続法(3人称)には注意ください。
さて次に Let’s でおなじみの「勧誘」も「命令法」の形をとります。
- (You) let us do it.(元の形)
- (You) let’s do it.(短縮形)
本来「勧誘」とは「一人称複数 we」を主語にして「私があなたと一緒にする行動を呼びかける」ことです。
実際にフランス語やドイツ語の勧誘表現では主語を「一人称複数」にします。
ではフランス語の命令法の形を aller(動詞の原形:英語の “go“)でみていきます。
- allez(2人称複数 vous が主語)
- va(2人称単数 tu が主語)
- allons(1人称複数 nous が主語)
フランス語の命令法は「動詞の原形(ここでは aller)」とは違う形を使います。
このようにフランス語では命令法とはよばれているものの、主語を nous(英語の we )に合わせて動詞の変化させ「勧誘」を表現します。
- Allons-y.(さあ、一緒に行こう)
- ムリヤリ英語:(We) go there.
- 英語訳:Let’s go.
もしその言語に「勧誘」を表す動詞の専用形がある場合は「勧奨法 cohortative mood」といいます。
わかりやすくいえば、勧奨法は「一緒にやろうよモード」と言っていいかもしれません。
ところが英語には「勧奨法(一緒にやろうよモード)」の専用形は動詞に存在しません。
そこで英語は「命令法」を応用して「一緒にやろうよモード」を表現します。
「勧誘」と「命令」を同じように扱うのは、さきほどのフランス語のようにヨーロッパ系の言語ではよくあることです。
ここで注意するポイントがあります。
(You)let us do の構造そのものは「命令法」だということです。
Let us の短縮形である Let’s には「命令」の意味はなくなり「勧誘」を表現することしかできません。
しかし Let us の場合は「勧誘」と「命令」の2種類を表現できます。
- 勧誘 :Let us go!
- ぼくらで一緒に行こう!
- 命令 :Let us go!
- (あなたは)我々を開放しろ!
この2つは会話の状況から区別できます。
- 勧誘:(You) Let us go!(我々で一緒に行こう!)
- 「話し手 I」が「会話の相手 you」を us に含めている
- You が us のグループ内
そして命令のケースは状況が変わります。
- 命令:(You) Let us go!(我々を開放しろ!)
- 「話し手 I」が「会話の相手 you」を us に含めていない
- You が us のグループ外
英語の「命令法」は基本的には「二人称 you」に対して使用される用語です。
ですがこれは文法用語の区分けであり、実は明確に分けられるものではありません。
なにより「命令」に関して重要なことは「これから起きる行動を期待する」というイメージです。
つまり「命令」は文法用語としては「勧誘・祈願」と近いグループに入ります。
- 二人称 you に期待する行動 ⇒ 命令法
- 一人称複数 we に期待する行動 ⇒ 命令法の応用(勧誘)
- 三人称 he she it they に期待する行動 ⇒ 仮定法現在(祈願)
ちなみにエスペラント語ではこれらすべて「意志法 volitive mood」で表現できます。
エスペラント語の場合「動詞の原形 + u」が「意志法」の専用形になります。
実際に「行く go」の動詞 iri(原形・不定形)の変化パターンを見てみます。
使い方は動詞の語尾の –i を現在時制 –as や未来時制 –os などに変化させるだけです。
不規則変化動詞は無く、すべてこの変化パターンなので超カンタンです!
- iri(原形 / 不定形 infinitive)*
- iras(現在時制 present tense)
- iris(過去時制 past tense)
- iros(未来時制 future tense)
- iru(意志法 volitive mood)
- irus(条件法 conditional mood)
エスペラント語の動詞は「時制」と「法」を分離して運用できます。
では主語をいろいろ変えてエスペラント語の「意志法」を見ていきます。
- 命令(2人称 + 意志法 )
- (Vi) iru. *”(You) + go”
- (あなたが)行きなさい。
- 勧誘(1人称複数 + 意志法 )
- Ni iru. *”We + go”
- 一緒に行きましょう。
- 祈願(3人称 + 意志法 )
- Li iru. *”He + go”
- 彼が行ってほしい(と話し手が考えている)。
実は英語もほぼ同じシステムで、これら3つすべて「動詞の原形」で表現しますよね?
- 命令(命令法)
- 勧誘(命令法の応用)
- 祈願(仮定法現在)
これらには「行動を期待する」という類似点があるからです。
つまり英語は「動詞の原形」で「これから行動が起こりそう」という「法 mood」を発動させています。
そのため聖書などには「動詞 let」の原形をつかった「命令・祈願」のような表現があります。
And God said, Let there be light: and there was light.
『そして God は言った、光あれ(≒ 光よ存在せよ)。そして光が生まれた。』
聖書 創世記一章三節(Genesis 1:3)
聖書の原文は「ヘブライ語 Hebrew(ユダヤ人の言葉)」で書かれていて、ここでは動詞の「指示法 jussive mood(三人称に対する命令)」が使われていました。
ヘブライ語と違って、英語には「指示法 jussive」の専用形がないので「動詞の原形(命令・祈願)」で代用しています。
細かいことを言えば “(You) let there be light.” なので「You ってだれやねん!?」となるはずです。
なぜならこの文章は「創世記 Genesis(世界が生まれる話)」で登場し、なにも存在しないところから「光」が生まれます。
つまり「光」が生まれる前の段階で「無」の中に you が既に存在することははありえないはずなんです。
そんな文法的にもツッコみどころがある文ですが、それはさておきヘブライ語の語感を尊重した表現として「動詞の原形 let」を受け止めるとよいと思います。
くわしくは Grammarphobia さんのブログを参照ください。
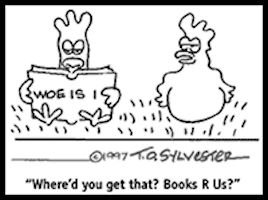
このように英語には様々な言語がまじりあっています。
そんな歴史の経緯から意味がほぼ同じものにも別々の文法用語がついていることがあります。
とはいえムリヤリ区別しなくてもエスペラント語の「意志法 volitive mood」のようにまとめられるのが英語の「動詞の原形」をつかった表現です。
英語を瞬時に的確に理解するには「動詞の形 verb form」から「話し手の判断・認識(法 mood)」を受け取ってください。
法助動詞の「法 mood」
では「法 mood」の最後のテーマ「法助動詞 modal (auxiliary) verb」を見ていきます。
英語の場合は「法助動詞」がいろいろな「法」を発動するエキスパートです。
- will 意志
- can 能力・可能性
- may 許可・選択肢
- shall 義務
- must 必然性
法助動詞の和訳はいろいろありますが「話し手の判断・認識」を動詞に追加できます。
ゲルマン語グループでは法助動詞の語源を共有しているのでここで紹介します。
意味はそれぞれ対応しているとは限らないので、あくまでも語源の参考でお願いいたします。

英語の法助動詞 will は「未来時制」と呼ばれる場合ありますが、これも「法」の機能の応用です。
英語の動詞は「未来形」に変化しないので厳密な「未来時制」は存在しません。
これは英語、ドイツ語、オランダ語などのゲルマン語グループの特徴です。
そこで「未来に○○するつもり」のような未来表現は「法助動詞」の現在形で代用します。

ドイツ語の未来表現は動詞 werden(英語の become に近い意味)をつかいます。
未来表現のために動詞の原形をサポートする動詞 werden は「法助動詞」ではありません。
動詞の原形とつながって「~することになる」という意味なので「助動詞」のグループとして扱われます。
これは過去分詞をサポートする動詞 sein (英語の be) や haben (英語の have) を「助動詞」と呼ぶのと同じことです。
ちなみに英語の will にあたるドイツ語の法助動詞 wollen は英語の「want to(~したい)」に近い意味になります。
英語の未来表現について詳しい解説はこちらをどうぞ。
さて昔の英語の法助動詞は、普通の動詞とほぼ同じ仕組みだったので「直説法」や「仮定法(接続法)」の形がありました。
現代ドイツ語は古英語と同じで「法助動詞」が動詞の機能をもっています。
そのためドイツ語の法助動詞 mögen(英語の may に近い)には「接続法Ⅱ式(英語の仮定法過去形)」の専用形 möchte が存在します。
しかし現代英語の法助動詞は「時制」の機能すらあやふやになってきています。
現代英語の法助動詞は「いろいろな『法 mood』を表現するエキスパート」という理解がうまく機能すると思います。
重要なのは「統語論 syntax」では英語の法助動詞は「定形動詞 finite verb」として機能していることです。

あえて古い表現で thou shalt(単数の you shall)をつかってみました。
こうすれば法助動詞が shalt ⇔ shall にように主語と連動する定形動詞であることがよくわかると思います。
③ 相 アスペクト Aspect
文法用語の「相 aspect」は「行動の進行度(実現度)」を表します。
英語の aspect はラテン語で「見ること、観察すること」を意味する aspectus に由来します。
つまり1つの行動に対して「スタートからゴールまで」どれほど進んでいるのか?をとらえる視点と考えてください。
英語に登場する「相」は3種類あり、行動の実現度(0~100%)を表現できます。
- 未然相 prospective aspect(0%)
- 進行相 progressive aspect(1~99%)
- 完了相 perfect aspect(100%)
それぞれの「相」を日本語にしてみます。
- 未然相:行動が予定されている(≒ まだやっていない)
- 進行相:行動が進行している(≒ まだ終わっていない)
- 完了相:行動が完了した(≒ いつ終わったかは関係ない)
英語の「相」は動詞の形容詞用法である「分詞」と「不定詞(形容詞用法)」で発動させます。
- 未然相:to do(不定詞)
- 進行相:doing(現在分詞)
- 完了相:done(過去分詞)
ここで過去分詞の注意点をお伝えしておきます。
過去分詞の機能である「受動態 passive voice」は「目的語を主語に変える」ことで発動します。
つまり「他動詞(目的語を持つ動詞)」の過去分詞にしか「受動態」は発動しません。
- 自動詞の過去分詞:完了相+能動態(目的語なし)
- 他動詞の過去分詞:完了相+受動態
受動態については「相 aspect」が終わった後で「態 voice」のところで解説します。
では「受動態」をあえて発動させないように自動詞 fall をつかって「相」を解説します。
- The bridge falls.
- その橋は落ちる。
ここから「相」を表現するために「不定詞」と「分詞」を使います。
- 不定詞 to fall:落ちることになる(未然相)
- 現在分詞 falling:落ちている(進行相)
- 過去分詞 fallen:落ちてしまった(完了相)
これらはすべて品詞は形容詞として扱います。
そのため第2文型 SVC の be動詞と組みわせて文を作ります。
- The bridge is to fall:その橋は落ちることになる。
- The bridge is falling:その橋は落ちている。
- The bridge is fallen:その橋は落ちてしまった。
実は上記の3つの文は文法解説を優先させてつくりました。
間違いではないのですが、古風だったり堅苦しかったりします。
そこで、現代英語でもなじみのある自然な英文にしてみます。
- The bridge is going to fall:その橋は落ちることになる。
- The bridge is falling:その橋は落ちている。
- The bridge has fallen:その橋は落ちてしまった。
この3つであれば普段よく見る英文に近づいたかと思います。
少し表現は変わっても「相」を表現できることは確認いただけるはずです。
時制と相の違い
現実として「相」は「時制」とよく似ているので、日本語では「過去」と「完了」はほぼ区別できません。
そのため「過去時制」と「現在完了」の違いは和訳だけではわかりにくいです。
これは日本語の「問題」ではなくて、言語ごとの「特徴」と考えてください。
例えばラテン語は「未完了時制」や「完了時制」といった「(相を含んだ)時制」を持ちます。

そのためラテン語の子孫のロマンス語の「時制」は「相」と区別するのが難しい性質を持っています。
ですが英語とエスペラント語は「時制(動詞の機能)」と「相(分詞の機能)」をきっちり区別するシステムを持っています。
つまり英語は「時制」と「相」を分けるだけで、とてもカンタンに理解できます。
- 時制 tense
- 行動がいつ行われるのか?を表現する
- 動詞を使って表現する
- 相 aspect
- 行動がどれほど進んだか?を表現する
- 分詞(動詞の形容詞変化形)を使って表現する
英語の持つ「非過去(まだ動く)」と「過去(もう動かない)」の2つの時制の区分は「相 aspect」にも発動します。

英語の動詞や分詞は「動く VS 動かない(現在 VS 過去)」の2種類が基本になります。
では「時制(動詞)」と「相(分詞)」を組み合わせて文を作ります。
- She is doing it.(現在時制+進行相)
- 彼女はそれをしています。
- ⇒ 現在、それを実行している
- She was doing it.(過去時制+進行相)
- 彼女はそれをしていました。
- ⇒ 過去、それを実行していた
- They have done it.(現在時制+完了相)
- 彼らはそれをしました。
- ⇒ 現在、それを実現しおえている
- They had done it.(過去時制+完了相)
- 彼らはそれをしました。
- ⇒ 過去、それを実現しおえていた
和訳だけでは英語をうまく表現できないので「時制 x 相」で理解していきましょう。
そうすれば「過去時制」と「現在時制+完了相」も区別できます。
- 過去、その行動を実行した(過去時制)
- 現在、その行動は実現している(現在時制+完了相)
分詞を助ける動詞 be & have
英語の be動詞や have は「分詞を助ける動詞」という意味で「助動詞」となります。
その理由は「分詞」が非定形動詞であるがゆえに単独で文をつくることができません。
そのため定形動詞が分詞のサポートとして絶対に必要になるからです。
- He is doing it.(現在時制+進行相)
- 動詞 is ⇒ 助ける定形動詞
- 現在分詞 doing ⇒ 非定形動詞
- They have done it.(現在時制+完了相)
- 動詞 have ⇒ 助ける定形動詞
- 過去分詞 done ⇒ 非定形動詞
では「統語論 syntax」と「意味論 semantics」で分析してみましょう。

このような分詞をつなぐための「助動詞」は「第一助動詞 primary auxiliary verb」とも呼ばれます。
本来であれば英語やドイツ語の文法は「法助動詞 modal (auxiliary) verb」と「第一助動詞 primary (auxiliary) verb」を区別します。
ちなみに英語の法助動詞はゲルマン語の特徴なのでドイツ語にはありますが、ロマンス語のフランス語に同じ仕組みはありません。
それでもドイツ語とフランス語で be と have と同じ機能を持つ動詞が過去分詞をサポートする場合は「助動詞」と呼びます。
- be(英)sein(独)être(仏)+過去分詞
- have(英)haben(独)avoir(仏)+過去分詞
英語と違って、ドイツ語やフランス語は日本で現在進行形と呼ぶ形がありません。
注意ですが “This is interesting.” のような進行相を発動しない現在分詞(実質ほぼ形容詞)のパターンならたくさんあります。
それゆえ「過去分詞」だけが be や have と連携して「完了相」を発動します。
一方で、イタリア語やスペイン語には英語と同じように「時制+進行相」を発動する形があります。
さて日本で「現在進行形」と呼ばれるものは「be動詞+現在分詞(SVC)」です。
現在進行形とひとまとめで呼ばれる理由は「複合時制 compound tense」という解釈がとられているからです。
複合時制については後述いたしますので、現在進行形とは「現在時制+進行相」と知っていればOKです。
そして「現在進行形」と同じく「現在完了形」も複合時制の一つです。
実際には「現在時制+完了相」という2つの機能を組み合わせています。
さて現在分詞と過去分詞を見てきましたが、この2つだけでは表現が限られてきます。
なぜなら英語には「未来分詞 future participle」が存在しないからです。
そのため英語は「未来分詞」の代わりをチームプレーによってつくります。
不定詞は「未来分詞」の代わり
英語に「未来時制」を発動する「動詞の未来形」は存在しません。
そのため法助動詞 will をつかって「未来への意志(現在時制+法)」を表現します。
さらに英語には「未然相」を発動する「未来分詞(未然分詞)」も存在しません。
ところがラテン語とエスペラント語には「未然相を発動する分詞」が存在します。
- 未来分詞 future participle(ラテン語)
- 未然分詞 prospective participle(エスペラント語)
ラテン語とエスペラント語は英語よりも多機能な動詞パラダイムを持っています。
そして言語のシステムからみると、英語にとってこの2つは強力なライバルなんです。
- ラテン語 Latin
- ローマの言語で中世から近代までのヨーロッパ世界の共通語
- エスペラント語 Esperanto
- 世界共通語をめざして作られた人工言語
現代の世界において英語は「事実上の世界言語 de facto lingua franca」となっています。
つまり、ほかの言語にできることを英語ができないと翻訳で困ってしまいます。
まして「世界共通語」としての可能性を備えた言語に、システムの不備で後れを取るわけにはいかないんです。
そこで英語は「不定詞 to do」をつかって「未来表現の分詞」と同じ機能を作ります。
- 未来表現の動詞(未来時制)の代用
- ⇒ 法助動詞 will
- 未来表現の分詞(未然相)の代用
- ⇒ 不定詞 to do
もともと不定詞は「前置詞 to」と「動詞の原形(名詞用法)」の組み合わせで使われていました。
ただ古英語の時代は「目的や結果」を意味する for doing に近い感覚でご理解ください。
そのため「○○することへ向けて」という「未然相 prospective aspect」を意味することが可能です。
日本の英文法解説でも「不定詞は未来志向」とよく書いてあるかと思います。
この「未来志向」は文法の機能で説明すると「未然相」となります。
これらのラテン語などの未来分詞の英訳には不定詞を組み込んだ表現がよく利用されます。
それは「~する方向へ(未然相)」という英語の不定詞の機能がうまく合うからです。
では英語・ラテン語・エスペラント語の「分詞」を比べてみましょう。

それぞれ文法用語は違うものの「相 aspect」を担当しているのは分詞です。
英語だけ「過去分詞」と呼ばれ、ほか2つは「完了分詞」になっていますが機能は同じです。
ドイツ語やフランス語の「過去分詞」でも機能は「完了相の分詞」という理解でOKです。
はっきりいって「直説法の時制」ではない文法用語の「現在・過去」は紛らわしすぎます。
そのためドイツ語文法では「Ⅰ式」と「Ⅱ式」をつかうものが増えています。
ドイツ語では接続法と同じく分詞にも「現在 ⇒ Ⅰ式」と「過去 ⇒ Ⅱ式」への切り替えがみられます。
- 日本語
- 現在分詞
- 過去分詞
- 英語
- present participle
- past participle
- ドイツ語
- Partizip I
- Partizip II
これらは用語は違いますが同じものを意味しています。
分詞に関して言うと、言語によって名称はバラついていますが機能はほぼ共通です。
現在と過去で下手に悩むぐらいなら I式 と II式 で区別するのもありかと思います。
もしくはエスペラント語に習って「機能重視の名称」もおぼえて損はないと思います。
- 進行分詞 progressive particple
- 完了分詞 perfect participle
なによりも仮定法と分詞の「現在・過去」は絶対に直説法時制と一緒にしないでください。
さてゲルマン語の英語やドイツ語には「未来分詞」がありません。
そのため「不定詞 to do」のチームプレーで対応しています。
古英語の不定詞 to do は「前置詞 to+動詞の名詞形」でした。
そのため分詞と違って文法書では「構文」として解説されることが多いです。
現代英語では形容詞用法の不定詞 to do の機能を「未然相」と解釈しても大きな問題は起きません。
では「未然相」の不定詞を使った表現を見ていきます。
英語の参考書などでは次の形で見つかるはずです。
- be going to(~するつもり)
- be to 構文(義務・運命・予定など)
- be about to(そろそろ~しそうである)
- be yet to(まだこれから~する)
英語の「不定詞の成り立ち」についてはこちらをどうぞ。
英語の不定詞の構文解説はなぜか to で止まった表現が一般的です。
私の見解では英語以外の言語を使う人たちが学ぶ時に、動詞の原形を使う位置をわかりやすくするためかと思われます。(あくまで推測です)
たとえばフランス語に代表されるロマンス語では、英語の「to 不定詞」や「法助動詞」でつくる表現は大きく仕組みが異なります。
ヨーロッパ系の言語では「動詞の原形(名詞用法)だけ」を動詞の目的語でとるのが多数派です。
そのため英語の want to や can そして be going to に当たる表現は、フランス語では「ホンモノの動詞」のあとに「動詞の原形(名詞用法)」を接続します。
- I want to speak French.(英)
- Je veux parler français.(仏)
- 私は 欲する 話すこと フランス語を(仏語の和訳)
- I can speak French.(英)
- Je peux parler français.(仏)
- 私は 能力を持つ 話すこと フランス語を(仏語の和訳)
- I am going to speak French.(英)
- Je vais parler français.(仏)
- 私は 向かう 話すこと フランス語を(仏語の和訳)
フランス語をベースにした場合は「英語はここに動詞の原形をおけばいいんやね!」と楽にわかります。
しかし英語は to do をまとめて「不定詞」として使うように変化した言語です。
統語論(Syntax)の理解のためには切り離すのはよくありません。
そこで英語の「不定詞」とわかるように to do まで表現を広げます。
- be going to do
- 『進んでいる+する方向へ』
- 進行相 going + 未然相 to do の連携表現
- be to do
- 『~する方向である』
- 古英語の用法に由来(義務・予定・運命など)
- be about to do
- 『~する方向のあたりである』
- 不定詞と「周辺 about」の連携表現
- be yet to do
- 『まだこれから~する予定である』
- 不定詞と「まだこれから yet」の連携表現
すべて「未然相(行動が行われる予定)」の応用パターンで機能します。
「不定詞 to do」と「未然相」の詳しい解説はこちらをどうぞ。
時制・法・相(TMA)vs 複合時制
ここまで重要な「相 aspect」という用語になじみがない方も多いかと思われます。
なぜなら日本の英文法解説の多くは「複合時制 compound tense」を採用しているからです。
複合時制とは「時制・法・相(TMA)」をぜんぶまとめて「時制」と解釈するものです。
伝統文法の解釈であれば複合時制をつかうと「動詞・法助動詞・分詞」はまとめて「述語動詞 V」になってしまいます。
実際に複合時制は「traditional grammar(伝統文法)」というギリシャ語やラテン語と相性のいい時制の解釈なんです。
In the traditional grammatical description of some languages, including English, many Romance languages, and Greek and Latin, “tense” or the equivalent term in that language refers to a set of inflected or periphrastic verb forms that express a combination of tense, aspect, and mood.
『英語、多くのロマンス語、ギリシャ語とラテン語などを含む言語の伝統文法の解釈では「時制 tense」もしくは「時制と同じ意味合いで使用される用語」が示しているのは「時制(tense)・相(aspect)・法(mood)」の組み合わせで表現される動詞やその補助となる品詞をひとまとめにしたもののことである。』
Tense-aspect-mood – Wikipedia
この「複合時制」がやっかいなのは「○○形」と呼ばれることが多いからです。
- 現在完了形 present perfect
- 過去進行形 past progressive
- 未来形 future
本来であれば英語の「形 form」は英単語の「変化する形(見た目)」のはずです。
- (名詞の)単数形 singular form
- (名詞の)複数形 plural form
- (動詞の)原形 base form
- (動詞の)現在形 present form
- (動詞の)過去形 past form
- 動詞の形 verb form
残念なことに日本の英文法解説では「複合時制」と「単語の形 form」の区別がごちゃごちゃになった解説をよくみます。
ではここから実際に日本で一般的な「時制(本当は複合時制)」を見ていきます。
- I do it.(現在形)
- I did it.(過去形)
- I will do it.(未来形)
- I am doing it. (現在進行形)
- I was doing it.(過去進行形)
- I will be doing it.(未来進行形)
- I have done it.(現在完了形)
- I had done it.(過去完了形)
- I will have done it.(未来完了形)
英語と相性の良くない複合時制ですが、実は中世~近代ヨーロッパの共通語だったラテン語だときれいにまとまります。
なぜならラテン語は1つの動詞だけで「時制・相・法」を表現する変化パターンをもつからです。
ラテン語の「時制」は「相 aspect」の性質が強く基本時制の6パターンを1つの動詞の変化で表現できます。
- Present 現在時制
- Future 未来時制
- Future Perfect 未来完了時制
- Perfect 完了時制
- Imperfect 未完了時制
- Pluperfect “大完了”時制 *大過去とよく言われますが意味は「大完了」です
つまり「複合時制」は未来も相も時制に含むラテン語と相性のいい文法解釈なんです。
昔は英文法の解説もラテン語をベースに行われていたので、英文法用語はラテン語からとられたものがほとんどです。
しかし英語はラテン語と動詞パラダイムの仕組みが違うので、複合時制をつかわないほうがわかりやすいです。
では英語の仕組みを優先して「複合時制」を TMAV で再構築します。
現在時制グループ
動詞の「現在形 present form」をつかって「現在時制(非過去)」を発動します。
現在分詞(進行相)や過去分詞(完了相)とも連携できます。
- I do it. 現在時制
- I am doing it. 現在時制+進行相
- I have done it. 現在時制+完了相
過去時制グループ
動詞の「過去形 past form」をつかって「過去時制」を発動します。
現在分詞(進行相)や過去分詞(完了相)との連携も可能です。
- I did it. 過去時制
- I was doing it. 過去時制+進行相
- I had done it. 過去時制+完了相
未来表現グループ
未来時制のない英語がつくる「未来表現」は2パターン可能です。
- 法助動詞 will(未来への意志)
- 不定詞 to do(未然相)
この2つは「時制(動詞)」と「相(分詞=形容詞)」の対応可能な形です。
- 動詞へ未来表現を追加:未来時制の動詞の代わりで使える
- 形容詞へ未来表現を追加:未然相の分詞の代わりで使える
ではこの2つを「複合時制」と比べていきます。
法助動詞 will の「未来への意志」は「法 mood」の機能です。
基本として will(現在形)と would(過去形)なので will は「現在時制(非過去)」です。
- I will do it. 未来への意志+動詞
- I will be doing it. 未来への意志+動詞+進行相
- I will have done it. 未来への意志+動詞+完了相
では次に「不定詞」をつかった「未然相」の未来表現を見ていきます。
一般的な表現では「未然相」の応用形は「be going to do」がよく利用されます。
この形の由来は「going (outside) to do」で「~するために(外に)出ようとしている」という表現でした。
現代英語では「場所の移動」の意味はなくなり、純粋に「~する方向へ向かっている(未然相の応用形)」で運用します。
では統語論文法の解釈をご紹介します。

私の統語論文法での解釈では、この「不定詞 to do」を歴史的経緯からみて「副詞用法」つまり文の要素に入らない「おまけ要素」としています。
不定詞の「未然相」は「現在(非過去)」と「過去」の2つの時制と組み合わせて使用できます。
- I am going to do it.(現在時制+進行相+未然相)
- 私はそれをするつもりです。
- I was going to do it.(過去時制+進行相+未然相)
- 私はそれをするつもりでした。
このように「複合時制」と呼ばれるものは「時制・法・相」の組みあわせです。
現代英語は「時制・法・相」が連携プレーで成り立つので、このことが分析型言語(analytic language)と呼ばれる大きな理由の一つになっています。
④ 態 ヴォイス Voice
文法用語の「態 voice」は「行動のする / される」を区別する文法用語です。
英語の voice は、ラテン語で「声」を意味する vox に由来し、この vox はラテン語の文法用語としての「態」も意味しています。
英語には2種類の「態」があります。
- 能動態 active voice
- 受動態 passive voice
まず主語と行動の関係が「~する」だった場合は「能動態」と呼びます。
- I eat here. *SV 能動態
- 私は 食事をする ここで。
- I eat an orange. *SVO 能動態
- 私は たべる オレンジを
次に主語と行動の関係が「~される」だった場合は「受動態」と呼びます。
- An orange is eaten. *SVC 受動態
- オレンジは たべられる(たべられた)
英語の受動態には過去分詞 eaten をつかう必要があります。
その理由は英語の「態」には日本語の「態」よりも厳しいルールが設定されているからです。
英語では「目的語 Object」を「主語 Subject」に変えなければ「受動態」を発動できません。
このことが意味するのは「受動態」には「他動詞の目的語」がまず必要ということです。
というわけで基準となる「他動詞の能動態」を軸に動詞と過去分詞を見ていきます。
自動詞と他動詞
能動態をつくる/ つくらない動詞は次のように区別されます。
- 自動詞:目的語をとらない動詞
- 他動詞:目的語をとる動詞
ちなみに文法用語で目的語をとる動詞の機能を「他動性 transitivity」と言います。
ラテン語の「trans 越える」という原義から「動詞の機能が名詞まで越えていく性質」と考えれば良いと思います。
- 自動詞 intrasitive:
- 意味が名詞に届かない(目的語にできない)
- 他動詞 transitive:
- 意味が名詞に届く(目的語にできる)
ただ英語の動詞は「自動詞 or 他動詞」を分けるだけでは十分に機能しません。
目的語の位置を理解するために「文の要素 SVOC」と「五文型 sentence patterns」の知識が必要になります。
- 自動詞 intransitive verb
- 第1文型 SV
- 第2文型 SVC
- 他動詞 transitive verb
- 第3文型 SVO
- 第4文型 SVOO
- 第5文型 SVOC
文の要素が作る五文型の仕組みはこちらを参照ください。
目的語をとるのは「他動詞」だけです。
これはつまり「他動詞の過去分詞」だけが「受動態」を発動できるということです。
- 能動態 active voice:自動詞と他動詞の機能
- 受動態 passive voice:他動詞の過去分詞の機能
英語だけでなくドイツ語やフランス語の「過去分詞」もこういう仕組みです。
そのため日本の中学英語の知識は現実では機能しません。
さらに残念なお話ですが、英語の動詞は「自動詞 / 他動詞」の区別がとても難しいんです。
なぜなら多くの英語の動詞は自動詞・他動詞のどちらも使えるからです。
- I cannot stand here. *自動詞 SV
- 私はここに立てない。
- I cannot stand him. *他動詞 SVO
- 私は彼に我慢ならない。
さらに目的語のあり・なしだけで話は終わりません。
なんと「自動詞の主語」と「他動詞の目的語」の2パターンをとる動詞もあります。
困ったことに主語と目的語を入れ替えることで「文構造」も切り替わるんです。
- The window broke.
- SV ~が壊れた
- その窓はこわれた。
- He broke the window.
- SVO ~を壊した
- 彼はその窓をこわした。
このような動詞を「能格動詞 ergative verb / labile verb」といい、英語にはこのパターンがかなりあります。
絶対にやってはダメなのが英語の動詞に「1つの意味と1つの文型」だけを当てはめることです。
英語の動詞は複数の文型を担当できるものがよくあるので、5文型のどのパターンにもうまく対応してください。
ここまで「態」の解説でしたが、過去分詞には「受動態」に加えて「完了相」も発動します。
ではここから「相 aspect」と「態 voice」を組み合わせて解説していきます。
相 と 態 の同時発動
英語の動詞と分詞(不定詞を含む)は TMAV の2つの機能を同時に発動できます。
- 英語の動詞
- 「時制 tense」と「法 mood」の同時発動
- 英語の分詞
- 「相 aspect」と「態 voice」の同時発動
実際には「能動態」は動詞に備わる機能です。
しかし「能動 ⇔ 受動」の切り替え機能は「分詞」にしかないので、ここで重点的に扱います。
では「分詞 participle」の機能である「相」と「態」を確認してみます。

英語は不定詞を使いますが、ラテン語は「未来分詞 future participle」をもつ言語です。
ラテン語の分詞の機能も英語とほぼ同じなので確認してみます。

ではわかりやすい「能動態」から見ていきます。
- 不定詞 to do
- 未然相+能動態
- 現在分詞 doing
- 進行相+能動態
不定詞も分詞も「形容詞」ですが、他動詞から変化させた場合は「目的語」をとる機能もあります。
では「現在時制+進行相」を例にして統語論文法 Syntax の解釈を見ていきます。

まず現在分詞 having は形容詞なので「補語 C」の位置で使用します。
そこから「進行相」と「能動態」を同時発動させて「目的語 O’」である名詞 lunch をつなぎます。
深く考えずとも、現在分詞や不定詞から五文型を追加発動するだけでOKです。
現在分詞と動名詞も含めたING形の統語論文法の解説はこちらをどうぞ。
ここからが本番の「受動態」に入っていきます。
英語では他動詞の過去分詞だけが受動態を発動可能です。
では統語論文法で「能動態 ⇒ 受動態」の切り替えを解説します。

過去分詞は形容詞なので「補語 C」に入れる形にすればうまくいきます。
ここでは「第3文型 SVO」しか紹介しませんが、ほかのパターンでも応用できます。
もちろん第4文型 SVOO や第5文型 SVOC やイディオム動詞なども受動態にできます。
受動態の仕組みの統語論文法による解説はこちらをご覧ください。
状態受動 vs 動作受動
過去分詞に対する日本の英語解説は表面的なものが多い印象です。
なかでもかなりリスクの高いものが次の解説です。
しつこくてスミマセンが英語の「分詞 Participle」は「相」と「態」を同時発動する機能を持ちます。
さらに英語だけでなくさきほどのラテン語のようにドイツ語やフランス語でも過去分詞には「完了相」と「受動態」のいずれの機能も存在します。
ドイツ語とフランス語の他動詞の過去分詞はこのことが分かっていないとまともに使用できません。
もし過去分詞に「完了」と「受身」のいずれか一つしか発動しないという思い込みがあるのだとしたら、今すぐ考えを切り替えてください。
- 自動詞の過去分詞は「完了相のみ」の機能を持つ
- 他動詞の過去分詞は「完了相」と「受動態」の機能を持つ
英語の過去分詞には1つ大きな問題があって「完了相」と「受動態」のどちらかだけを使いたいときもあります。
そんなときでも残念ながら「他動詞の過去分詞」を使わざるを得ないんです。
なぜなら英語の場合は「完了相」も「受動態」も過去分詞だけが持つ機能だからです。
ではどんなことが起こるのか英語 Wikipedia から英文を借りてきて解説します。
たとえば「餌をあげる」という動詞 feed(変化パターン feed – fed – fed )を例にとります。
- The dog is fed.
- その犬はもう餌を与えられた。
このようなシンプルな形だと「完了相+受動態」の同時発動になってしまいます。
日本にはこの形を「受動態のみ」とする解説も多くあるでしょうが「完了相」を否定できる理由はありません。
実際に文法用語には「過去分詞」のどちらの機能が優先なのかを区別できるものがあります。
- 動作受動 dynamic passive:受動態の動作が中心
- 状態受動 stative passive: 完了相の状態が中心
この「状態受動」というのは「動作が完了されたあとの状態」を表現する用語です。
それゆえ「状態受動の過去分詞」は「完了相を意味する形容詞」と理解して大丈夫です。
そして、なんとドイツ語やスペイン語などはこの2つを文法上区別する仕組みを持ちます。
当然ですが、ドイツ語でもスペイン語でも「他動詞の過去分詞」だけが「受動態」を発動できます。
ドイツ語は「sein “英語の be”」と「werden “英語の become”」の違いで区別します。
- 動作受動 werden + 他動詞の過去分詞
- 状態受動 sein + 他動詞の過去分詞
そしてスペイン語には be動詞にあたるものは2種類あり、これらを過去分詞と組み合わせます。
- ser ⇒ 動作受動に使用(一般的にはこちら)
- ester ⇒ 状態受動に使用(動作完了後の状態を説明)
このように「動作受動 vs 状態受動」の切り替えができる理由は、他動詞の過去分詞が「完了相」と「受動態」の両方の機能を発動できるからです。
ところが英語の場合は「be + 過去分詞」がどちらでも基本の形で使われます。
ときおり「get + 過去分詞」もありますが、明確な区別ができているとは言えません。
- Stay here or you will be attached by a bear.
- Stay here or you will get attached by a bear.
- ここにいなさい、でないとクマに攻撃されることになるよ。
この「get vs be」は過去分詞に限らず、普通の形容詞でも利用できます。
- be +補語 C = 状態の説明がわかりやすい
- get +補語 C:状態の変化がわかりやすい
残念ながら英語はドイツ語やスペイン語のように明確に区別する仕組みがないので仕方ありません。
それゆえ英語は「動詞+過去分詞」ではない部分をつかって区別しようとします。
- 動作受動(受動態の機能)
- The dog is fed twice a day.
- その犬は餌をもらう 1日に2回
- ⇒ 受身の動作が中心なので動詞っぽく解釈する
- 状態受動(完了相の機能)
- The dog is fed so we can leave now.
- その犬はもう餌をもらった それで我々は今から出かけられる
- ⇒ 完了状態が中心なので形容詞っぽく解釈する
英語は「be + 他動詞の過去分詞」を「文脈」によって区別します。
もちろん「両方」発動する場合もあるので注意です。
- The task is already finished by him.
- その仕事はすでに彼によって仕上げられた。
- ⇒ 過去分詞 finished に「動作受動 & 状態受動」の同時発動
フランス語は英語と同じように「状態受動」と「動作受動」を明確に区別できません。
そのため英語もフランス語も過去分詞の意味をしっかりと考える必要があります。
とにもかくにも過去分詞がある英文和訳の丸暗記だけはやめておきましょう。
相 x 態の応用表現
英語は「動詞」と「分詞」で TMAV の機能を分担できるので、わかりやすくて便利な動詞パラダイムを持ちます。
ところが英語を超える動詞パラダイムの機能を持つ言語が存在します。
それが世界共通語を目指して作られた人工言語である「エスペラント語 Esperanto」です。

エスペラント語の分詞は英語よりも多くの機能を標準搭載しています。

これらすべて英語の be動詞にあたる「esti(動詞の原形で時制・法により変化)」につなげるだけで使えます。
エスペラント語の分詞の変化パターンはこうなります。

エスペラント語では英語でいうところの直接目的語(正確には対格 accusative case といいます)にあたる名詞の語尾に n をつけて区別します。
分詞も同じように「能動 or 受動」の切り替えは「対格のしるし n」のあり・なしでOKです。
エスペラント語は「動詞パラダイムの究極形」とも思える柔軟な構造をもっています。
相と態の切り替えだけでなく、分詞の語尾を変化させて品詞を切り替えることもできます。
- 分詞+a:形容詞 adjective
- 分詞+o:名詞 noun
- 分詞+e:副詞 adverb
つまりエスペラント語は TMAV に加えて品詞の切り替えすらも自由自在です。
残念ながら英語はエスペラント語ほど動詞を柔軟に運用できません。
しかし英語は世界言語としての責任を果たさなければならないので、軽々とエスペラント語に屈するわけにはいきません。
そこで分析型言語の英語はチームプレーによってエスペラント語の分詞に匹敵する機能を発動させます。

英文法書でよくみるこれらの形は「相と態」の連携表現です。
日本の英文法は「相 aspect」を複合時制に組み込んで「〇〇形」と呼ぶので、分詞の連携表現の仕組みが見えにくいです。
過去分詞の品詞は「形容詞」なので「be動詞(SVC)」から連結する形が基本です。
もちろん第2文型 SVC の「補語 C」で使えればよいので「get + 過去分詞」もよく使います。
- be + 過去分詞(基本形)
- get + 過去分詞(変化を重視する形)
では究極レベルの動詞パラダイムを誇るエスペラント語に負けないように、英語を TMAV の連携プレーで再解釈していきましょう。
① 未然相 + 受動態
「未然相 + 受動態」は「不定詞」と「他動詞の過去分詞」で表現します。

- The system is going to be updated soon.
- そのシステムはすぐにアップデートされることになるよ。
- Is the season 3 is going to get released?
- (その作品の)シーズン3って今後配信されるのかな?
だいたいこんな感じでつかえばOKです。
ほかにも決まったフレーズでも使用されています。
- to be continued
- 次回へつづく(継続される予定)
- to be determined(TBD)
- 未定(決定される予定)
- to be announced(TBA)
- 後日発表(発表される予定)
- to be confirmed(TBC)
- 確認待ち(確認される予定)
これらすべて「未然+受動」で「~される方向へ」を意味する構造です。
和訳を覚えるよりも英語の構造のまま意味を理解するほうが良いと思います。
また不定詞は「名詞・形容詞・副詞」の品詞としての機能をもちます。
エスペラント語と違って英語は「使用ルール」で品詞の切り替えを行います。
- 名詞用法(Nominal)
- 主語 Subject
- 補語 Complement
- 目的語 Object
- (✖)前置詞とペア ⇒ 動名詞の専用機能
- 形容詞用法(Adjectival)
- 補語(叙述用法 Predicative)
- 名詞を説明(限定用法 Attributive)
- 副詞用法(Adverbial)
- おまけ要素(文の要素に入らない)
- 形容詞を説明⇒ 不定詞の専用機能*一部例外
これらのうち、すべての不定詞が「未然相」を持つわけではないので注意ください。
特に「形容詞を説明」には「未然相」は基本的に適用しないほうが良いと思います。
- I am happy to see you.
- 私は = 嬉しい 会えて あなたに
形容詞につながる不定詞は、古英語では「理由」を導く表現でつかわれていました。
そのため for doing と似た解釈が可能になるので「未然相」は発動させないように解釈するとよいです。
② 進行相 + 受動態
「進行相 + 受動態」は「現在分詞」と「他動詞の過去分詞」で表現します。

- A new program is being installed now.
- 新しいプログラムがいまインストールされているところだよ。
- The next episode is getting delayed.
- 次回のエピソード(の発表・配信など)が遅延され続けている。
動詞のING形は名称は異なりますが「名詞・形容詞・副詞」の品詞としての機能をもちます。
- 名詞用法(動名詞 gerund)
- 主語 Subject
- 補語 Complement
- 目的語 Object
- 前置詞とペア ⇒ 動名詞の専用機能
- 形容詞用法(現在分詞 present participle)
- 補語(叙述用法 Predicative)
- 名詞を説明(限定用法 Attributive)
- 副詞用法(分詞構文/分詞節 Participle Clause)
- おまけ要素(文の要素に入らない)
- (△)形容詞を説明 ⇒ 不定詞の専用機能*一部例外
動名詞は「名詞用法」としての機能が強いので「~すること」という意味が軸になります。
そのため「進行相」の機能は「現在分詞」を中心に考えるほうが良いと思います。
動詞のING形の種類ごとの違いはこちらを参照ください。
③ 完了相 + 能動態
ここまでは過去分詞の「受動態」の応用でしたが、ここからは「完了相」の応用になります。
この「完了相 + 能動態」は have + 過去分詞というヘンテコな形で作ります。

日本だと現在完了や過去完了として「時制(複合時制)」で学ぶものです。
このパターンでは「have + 過去分詞」をまとめて「動詞」として扱います。
動詞 have と連携すると「他動詞の過去分詞」が「受動態 ⇒ 能動態」へと切り替わります。
- I have done it.(現在時制+完了相+能動態)
- I had done it.(過去時制+完了相+能動態)
この現在完了の最大のミステリーは「なぜ have を使うのか?」という理由です。
実はこの have は例外用法が関係していて、ややこしい歴史があります。
過去分詞が be と have のどちらとも連携できる理由を知りたい方はこちらをどうぞ。
この「have + 過去分詞」には「統語論文法 Syntax」から見ればヘンテコなところがあるのは事実です。
そのため文法用語として「能動 active voice」を入れたほうが誤解が少ないと思います。
- 現在完了形 ⇒ 能動完了の現在形
- 過去完了形 ⇒ 能動完了の過去形
ここまでわかれば、あとは「have+過去分詞」をまとめて動詞として解釈し、過去分詞から五文型パターンをつなげばOKです。
- History has taught us a lot of lessons.
- 歴史は我々にこれまで多くの教訓を与えてくれた。
- 第4文型 SVOO 能動態
- Her presence has made the future bright.
- 彼女の存在が未来を明るいものにしてくれた。
- 第5文型 SVOC 能動態
もちろん自動詞の時は目的語がなくなります。
- I have been here all day. *SV
- I have been sick all day. *SVC
そして最後のポイントは「have been 他動詞の過去分詞」の形です。
英語の have+過去分詞は「動作の強調」の機能も持ちます。
そこから「他動詞の過去分詞」と連携させてみます。
- Mr. President has been shot!
- 大統領が狙撃されました!
この形は「動作受動の強調表現」として理解することができます。
もちろん完了相は「経験」や「継続」でも解釈できるので、和訳にこだわらず柔軟に意味をとらえてください。
このように過去分詞には多くの機能があるので「意味論文法 Semantics」と「統語論文法 Synatx」の2つの視点から正確に見切ってください。
お疲れ様でした!
ここまで長いブログを読んでいただきありがとうございました。
英語の動詞パラダイムは連係プレーで機能するシステムです。
そのため個別の解説の寄せ集めではうまく説明できません。
時間はかかると思いますが、すこしずつ解きほぐすように読んでいただければ幸いです。
ちょっとユニークな英語塾
志塾あるま・まーたは、英語が苦手な方でも楽しく学べるオンライン英語塾です。
高校を半年で中退した塾長が、アメリカ留学中にエスペラント語と出会ったことをきっかけに、ゼロから“世界で通用する英語力”を習得できました。
その学び方をベースに、統語論(Syntax)と意味論(Semantics)を組み合わせた独自の指導法を展開しています。
さらにラテン語などヨーロッパ系言語の知識や、古英語・中英語を含む英語史の視点も取り入れた、ちょっとユニークで本格派な英語学習法をご紹介しています。
あるま・まーたの英語の学び方に興味を持っていただけたなら、ぜひお問い合わせください!
ブログの感想や英語の疑問・質問などでもお気軽にどうぞ!













